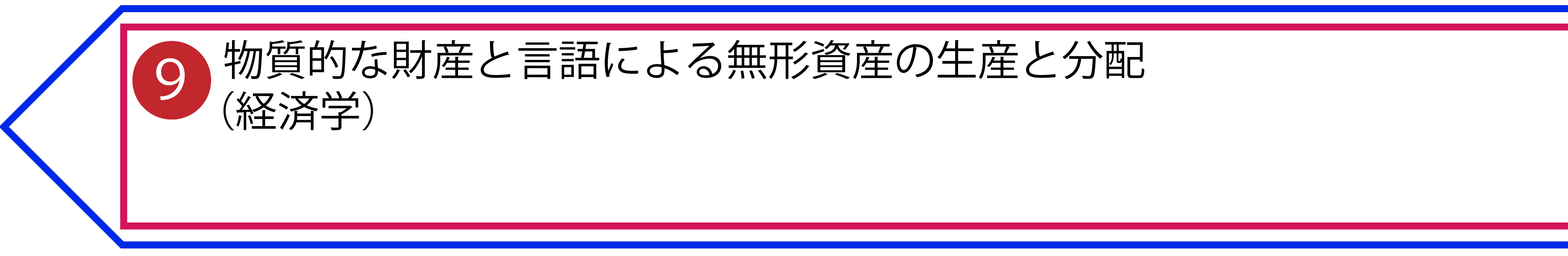
目次
- 区分(9)の定義
- 区分(9)の構成要素
- 区分(9)の形成過程
- 関連する学問分野
- 人が物に期待すること
- 物資源と人の関係
- 生物的環境と物的環境の深い関わり
- 言語と文字情報と物の力
- 物を中心とした秩序
- 集団の秩序と他者との関わり
- 区分(9)の発展と現代
- 関連する項目
区分(9)の定義
物的環境(B)の内的秩序の区分(9)の定義について。
自然環境(A)に存在する個人の手の届く範囲にある物に加えて、個人の身体を支える地面も含める。
人は自然物と人工物の区別なく、空間にあるあらゆる物から恩恵を受け利用して生きている。それらの物を指す概念を物的環境(B)の内的秩序と定義する。
注意点としては地面は内的秩序に含まれる一方で高い山や壁は障害として外的環境に含まれることだ。この意味で内外の明確な区分は存在しないと言っても良いだろう。(2022/6/15)
区分(9)の構成要素
物的環境(B)の内的秩序とは。
人が手が届く範囲の利用可能な物質全般と、手を加えて作り出した道具を始めとする人工物によって形成される環境層。
該当する環境要素は経済資源全般、文明、産業、工場、都市、パソコンなどである。主に人が生活する場所に存在して、生物的環境(B)の内的秩序の多様性に追従するようにと量産化と複雑化を果たした。(2020/6/26)
区分(9)の形成過程とはたらき
物的環境(B)の内的秩序と外的環境について。
主体は個人が属する集団(生物的環境の内的秩序)だ。その周辺にあって手が届く範囲の物質全てを指す。これは概念を言語のみで述べるだけではなく、具体例を挙げることで構造の立体感が伝わるだろう。
山や川や石や土、大地や植物は多くの動物にとって重要な生息条件だ。よって物的環境(B)から生物的環境(C)への影響を示す区分⇧10は全生物に及ぶ。
しかし、物的環境(B)に対しての影響を示す区分⇩41は他生物に比べて人からの働きかけが圧倒的に多い。その働きかけを通じて物的環境の内的秩序は巨大になった。
原初の時代には生態的な活動の余暇から物に働きかけていたものが、偶然の結果から得られた利益を知った後は、意図をもって物や他者や生物に働きかけるようになった。
それが記憶や経験から伝承、慣習となり秩序が形成された。
当初は物的環境に対する⇩41は微々たるものであったが、一方で自然環境が元来もつ物的環境からの⇧10は豊かな生命を生み出し続けた。その後、文明が発展するに従い物的環境に対する⇩は積み重なり、従来よりも繁殖と食料供給が促進されることになる。
物的環境の内的秩序は生物を除いた自然物を全て含めた環境区分であり、生態系の下地となる環境要素だ。生物にとっては生息環境、人にとってはいわゆる生活環境を意味するものだ。
生活環境において素手で物に働きかけることを始めとして、道具や言語、他者(命令や組織)を用いて物に働きかける行動は全て物的環境の内的秩序に含まれる。
その中でも人同士で行われる物の流通は内的秩序に区分される。そして道具を用いて異なる物資源へ働きかける作用は外的環境に向けて行われることで、物資源は新たに生産物として内的秩序へ取り込まれる。(2022/10/8)
区分(9)に関連する学問分野
現代人は物的環境(B)の内的秩序に招き入れた生産物が沢山ある。物的環境の内的秩序には人工物である建物や都市も当然含まれる。
生産物などの経済資源によって形成された秩序が存在するのが人の特徴である。他生物にとっての物的環境の内的秩序と呼べるものは巣穴やナワバリ程度である。
この物的環境の内的秩序の区分に該当する学問分野は非常に広いが、物資を媒介に成立する秩序について述べた経済学が代表的なものだ。(2022/11/22)
[wikiより「経済学」とは、経済現象の法則を研究する学問、人間社会における物質的な財産の生産と分配の法則を研究する学問である]
物的環境の内的秩序の区分(9)は物やそれを表す文字や概念を媒体とした集団の秩序を意味する。(2022/11/26)
人が物に期待すること
人と物の関係性については「物に期待する特定の性質を、その物を取り扱う行動を通して引き出して利用する」という一定の法則がある。
物に触れて取り扱った経験を通じてその物からどのような性質、機能、結果を引き出せるかを知り、その行動の結果を期待できるようになる。これが物に関する知識であり、物的環境の内的秩序を成立させている。(2022/6/22)
物資源と人の関係
人間や他生物ではない物資源に頼り、利用して、得られるエネルギー量を高めて大量消費を可能とする。
物資源を媒介にした経済活動により、利害の一致した集団の規模は大きくなる。その集団の成員同士の関係が対等ではなく主従の関係、かつては奴隷も含まれたとしても、それは物資源に支えられた集団と言える。奴隷を集団の一員に組み込むために利用する物資源は武器や檻、鎖などであろう。
利害の一致した集団を維持するために物資源から得られるエネルギーが大量に用いられた。こうして物的環境(B)の内的秩序が発展することにより様々な生産物を一つの経済的枠組みに収めることが可能になったのだ。国家を支える経済活動、産業の本質だ。(2020/7/24)
生物的環境(C)と物的環境(B)の深い関わり
人は物的環境(B)に働きかけて道具や価値ある物を作り出すことを覚えた。そして、その道具の性質が進歩するのに伴いより強い力を生み出すようになる。
物資を利用して自らの身体能力の制限を超えた力を扱えるようになったのだ。
こうして強い力を得た人間は、更に生物的環境(C)の外的環境にまで影響を及ぼすようになる。この影響は区分⇧10の現象にあたる。
直接的に生物を操作するのではなく道具を介した間接的な働きかけである点をこの概要図上の関係は示していることに着目して欲しい。
それとは別に生物や人に対して行われる道具を介した直接的な働きかけも物的環境(B)の内的秩序で起こっている。これは人以外の生物では見られない生物間の関係だ。
物的環境(B)の内的秩序の拡大によって築かれた人工の生物的環境(C)は、原生の生態系の一部であった人の群れと他生物の関係を超える程の大きな影響を与える。
分かりやすい例が濃厚牧畜の食料供給システムの整備を要因とした人口爆発だ。
この例以外にも、物的環境(B)の内的秩序の成熟に伴い、恐ろしいほどに強まった力により制御、管理される現代人の有り様が見えてくる。主に人同士の感情のみを基礎に結びついて野生動物を捕らえていた原始時代の人の集団とは違う。
しかしながら、この物的環境を介した生物間の関係と生身の身体間の関係をハッキリと分けることはできない。それでも物的環境の強い力を背景にした人の集団が成立したことは特別な意味を持つ。
これは現代の罰則を伴う法律によって支えられる社会集団や太古における武力による支配関係が築かれる部族間や奴隷の制度にも通底する原理だ。これによってより大きな集団の成立が可能となった。
人が他者を物の力により管理・支配する構造は、人が環境要素へ働きかける「帰りの流れ」によって成立する。
その背景となるのは物的環境の内的秩序に取り込んだ物資源の強い力、強力な兵器や高度な工業技術など生身の人ではとても出せないほどの力なのだ。(2020/8/5)
言語と文字情報と物の力
物的環境(B)に築き上げられた産業や経済システムの人の営みにもたらす恩恵は計り知れない。しかしコロナ危機による一部の産業の空洞化に見られるように物的環境の内的秩序の背景は目まぐるしく変化する。
その変化を推進する強い力を生み出すのが言語に基づく認知の体系だ。
原始時代の人の集団が何度も同じ場所を歩き通過することで獣道のように定まった道ができた。その道を集団を構成する各個体が認知することで道という言語情報の素ができる。こうして言語情報は集団の成員同士が行動や事物を示すための合図や象徴として現れた。
この例から分かるように人が自然物との関わりの中で発生した概念が言語として現れたことから、言語の有り様は主に自然環境(A)〜生物的環境(C)の影響下にあると言える。特に文字を含む環境層である物的環境(B)が様々な言語を生み出す事象・事物の中心的な役割を果たす。
自然環境(A)〜生物的環境(C)に存在する事象・事物に意味や価値を与えることで人同士のやりとりや物の流通を円滑にすることが言語(文字情報)の役割だ。
集団内において他者と物のやり取りをする手段として、その集団で共有される意味や価値を言語を用いて示すことで対価とすることがある。つまり言語を用いた約束事だ。
これが言語(文字情報)の役割であり、この約束事を利用して個人は「自由な行動」を摂取しているとでも言うべきか。
言語(文字情報)に規定されてしまう行動は自由と呼べないと言う向きもあろう。それでも欲望のままに自由な行動を取ることは当然に得られるものではないことを考えれば、行為を摂取する道筋の整備には意味があると分かるだろう。分かりやすい例として法の整備の恩恵が挙げられる。
これが言語に基づく認知の体系の力だ。(2020/7/7)
物を中心とした秩序
力の不均等な者同士の協調を物が媒介している。
個人が物を使ってその不均等をどのように解消するかが問題だ。個人の持つ力が不均等であっても争い生命を損なうことなく協調できる仕組みとは何か。
「物を中心とした秩序」という重要概念について。
特定の物資の機能や性質に対して期待する内容を共有する複数の人が存在する状態。
これが「物を中心とした秩序」である。そして物と人が結びつけば創造により大きな新たな価値が生み出される。これもまた物を中心とした秩序を推進する。
土地・物・生物・肉体・人に見出す価値や性質を認識した上で、それを引き出すことを期待して働きかける。この価値を引き出す一連の行動が物を中心とした秩序の現れと言えるだろう。
その事象・事物に期待する性質を共有すること。これは人同士だから可能であり、その価値観が共有されることで集団には秩序が生まれる。
秩序の形成過程には争いが少なからず存在して、その物の価値の恩恵をめぐって争うことを通じて新たな秩序が絶えず生み出されている。価値観を共有する複数の存在がいるとはそういうことだ。
物を中心とした秩序とは、その物を巡り複数人が争った結果として現れるものだ。争いを通じて、その物を手に入れて保持するためにどの程度の人員がどのような行為をする必要があるかを知ることで秩序は築かれるのだ。
こうして物的環境(B)の内的秩序は歴史を通じた物と人との関わりの軌跡として形成される。物的環境に限らず、各環境層の内的秩序にはその個人が生きるための秩序の素が組み込まれている。それは何に価値を感じ、何を必要とするかの傾向であり、同じ価値を受け継いできた祖先によって築かれた体系も影響する。
人は概ね既存の秩序の運用をし続けることで一生を終える。その秩序はいかにして生まれ、いかに維持されているかを遡ると、物や事象に対する価値観の共有へ辿り着く。
人は物を共有する巨大な集団組織である現代社会を作り上げており、そこに至るまでは物を巡り争う中で秩序が形成される過程があった。このことが意味するのは、人にとっての物の価値は人が争う労力の量に換算することでしか捉えられないということである。事象の結果によってしか事物の価値を決められない人の想像力の限界が見える。
以上で最も伝えたい主旨の一つに到達した。
経済活動も戦争も、人と物の関わりの表れである。これが秩序の形成過程だ。
その秩序とは物を人の集団で共同管理するために形成された。人は物の価値に従い、物に操られる体系の中に居りそれを運用しているのだと分かる。組織における人を機械の歯車に例えるのはよくあるが、この例はもっと広く社会の仕組みについても言えるのだろう。(2022/6/20)
集団の秩序と他者との関わり
個人が集団の秩序を内面化して、集団の一部として、集団全体の力を通して得た利益を利用するという構図。社会学でいう社会的役割の内面化だ。
秩序を内面に取り込んでいなくても、多くの工業生産物に囲まれて利用している現代人は、集団の秩序を間接的に利用して手足の延長として利用しているといえる。
回りくどい言い方だが、個人が他者を自分の手足の延長として利用しているのではなく、個人が集団の秩序を通じて他者を利用しているのだ。(2022/8/10)
区分(9)の発展と現代
縦の行きの流れ(↑)において、原始の裸の人類には物的環境の内的秩序と文字情報は存在しなかった。
現在ある物的環境の内的秩序と文字情報は共に帰りの流れの積み重ねによって構築されたものだ。現代人は過去の人が作り上げた内的秩序を足掛かりに行きの流れに乗っているだけとも言える。
よって、意識せずに受け入れているものが行きの流れに多く含まれている。過去に様々な意図をもって帰りの流れで働きかけた環境要素の中に、無意識に存在しているのが私たちだ。(2021/1/28)
関連する項目
(9)に関連のある42区分を以下に示す。
・⇧10 生息環境と生物や食料の関係
・⇨8 物資源の利用と消費
(9)に関連のある用語について述べたページを以下に示す。
・物的環境(B)
・内的秩序
考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。
・4つの流れ理論
