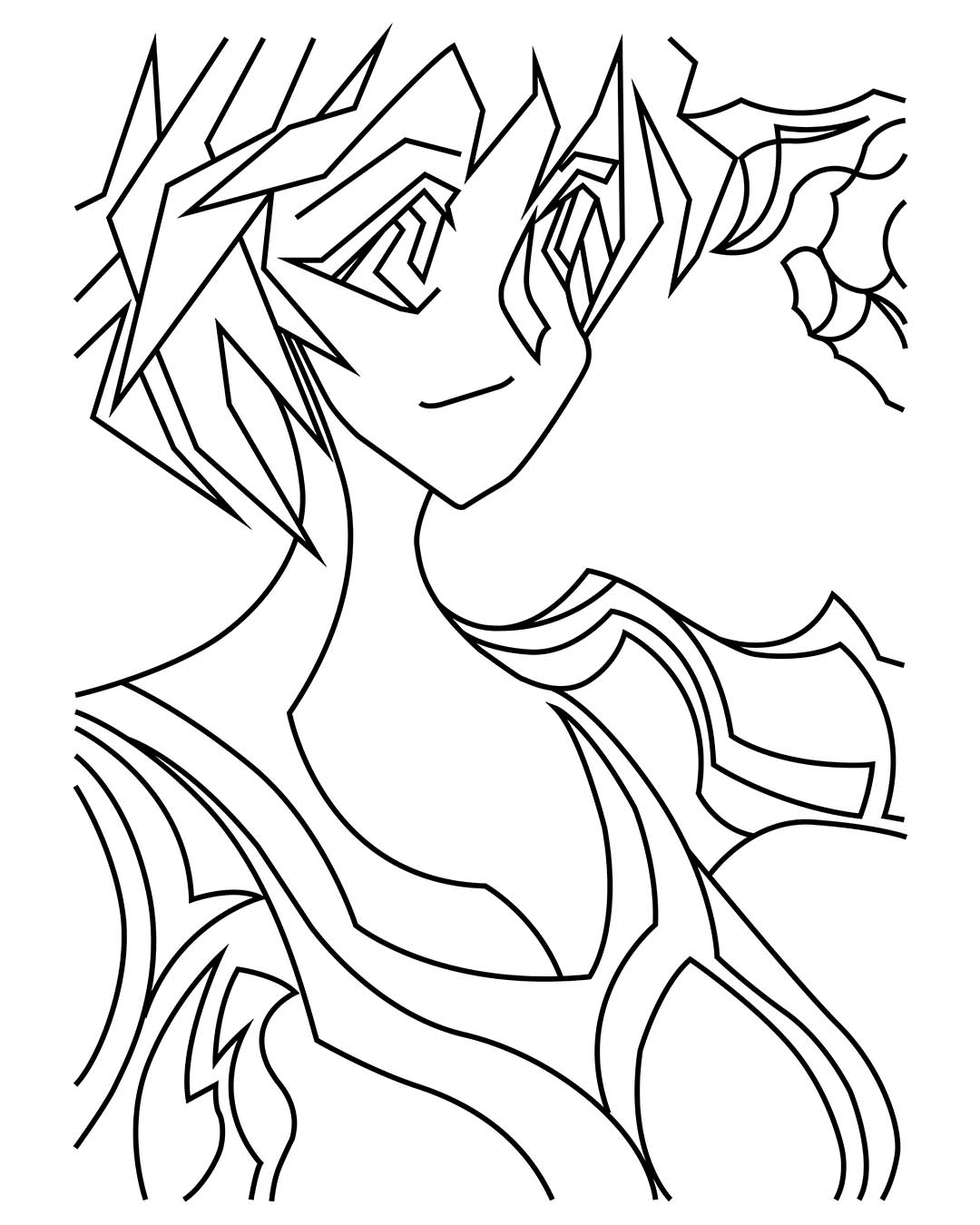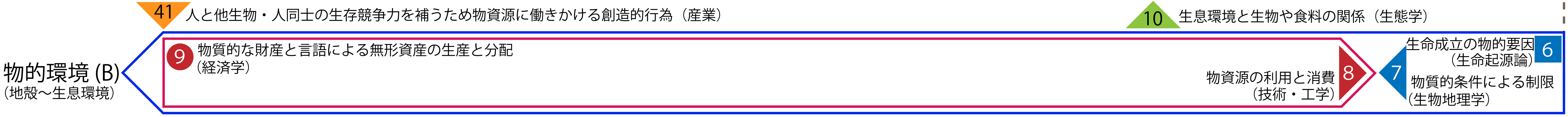
目次
- 物的環境(B)の定義
- 物的環境(B)の簡単な例
- 物的環境(B)と他の層の入れ子関係
- 文字と物的環境(B)
- 物的環境(B)の「文字情報」の表記
- 「言語に基づく認知の体系」と文字情報
- 物的環境(B)と言語の関わり
- 物の枯渇と人の協力
- 物と人の関係
- 関連する項目
環境層の区分 物的環境(B)の定義
個人の周囲に存在するあらゆる物質の中で、食料となる生物と他の人間を除いたもの。その内で人が行為によって影響を及ぼし状態を変化させたり、利用して益を得ることのできるもの。
それは「行き」の流れにおいて、人が望んだ行為を有効に成立させるために、益をもたらすものと障害となるものが混在した環境条件となる。これらの物によって形成されるのが物的環境(B)という区分だ。(2020/7/23)
物的環境(B)の簡単な例
物資源は加工して積み上げて価値を増やすことで人間関係を作り、発展させる。
木の小屋から始まり獲物を捕らえる武器、道具、食料を保管する入れ物、装飾品、便利なもの、強い力、美しい物、賢くなる物、便利な道路など。生物的環境(C)とも密接に繋がりながら、物的環境(B)も価値を積み上げてゆく。この「価値」という概念が重要になるのは人的環境(F)になってからだ。(2020/7/3)
物的環境(B)と他の層との入れ子関係
生物的環境(C)において人の集団は個人の余剰エネルギーを効率的に集めて総体としての力を高める。その力は物的環境(B)に影響を与える。生物の仕組みを例にすると、物資源を集団の内面に取り込み分解して、循環させたり代謝を行うようなものだ。これは原初の人類にとっては簡単な道具を石や植物から作り出し利用するところから、現代では産業を起こし経済によって物資源を消費する営みにあたる。
身体内で分解して摂取するエネルギーから、身体そのものを動かして得るエネルギーへと段階を移し、身体から離れた物質(生物)に働きかけ、その物質の恩恵を搾取して力を得る。この流れが入れ子構造になっていることが理解できるだろう。
原始の人類が群れを作って他の多数の個体に守られて暮らす段階から進み、物資源を手足を使い利用して、その働きやエネルギーの恵みによって暮らすようになる。
こうして人は物に包まれて暮らす生活を手に入れた。
最初は毛皮を身にまとう所から始まり、住居を作り、集落を作り、城を作り、武器を作り、畑を作り、工場を作り、強固な物資源に包まれるようになる。
ここに至っても一見は物的環境(B)に包まれているように見えて、実際は生物的環境(C)の中に物的環境(B)が取り込まれている構造は先の例に倣うところだ。
科学技術が進歩して人工の構造物に囲まれて便利な暮らしをしていると忘れがちだが、そもそも巨大な産業と経済システムは農耕文明によって著しく改善した生物的環境(C)を下地として発生したものだ。この生物的環境(C)の余剰エネルギーの調整のために物資源が利用されているのである。
しかし、肉体環境(E)や生物的環境(C)や自然環境(A)に災害や疫病などの異常が生じれば、余剰の力は減少する。そして従来の物的環境(B)の内的秩序が持つ余剰を調整する機能が正常に働かなくなる。実際にコロナ危機で経済活動が麻痺する事態が起きた。
もちろん全てが機能しなくなるわけではない、自然環境(A)に対し堅固な建造物は風雨から身を守り体温の安定を保つ助けとなる。
それにより肉体環境(E)は長時間危険から身を守られて安全で居られる。生物的環境(C)においても安定的に動植物を食料として摂取できる。こうして人は安定した食料供給に支えられて集団内で争わずに安定した秩序を維持できる。(2020/7/7)
文字と物的環境(B)
文字(とそれによって表される言語)は物の一種として認識される。文字情報は物の延長や代替のような存在として扱われる。
さらに正確に述べると言語とは事象、事物をめぐって他者と相対する時に使用する合図である。それは事物の内容が他者に伝わることを目的とするものだ。言語学などを通じてその機能や役割について深い研究がされていると思う。しかし、ここでは話をシンプルに割り切りやすく考えるために言語を表す文字を物の一種、物の派生物にすぎないものと仮定する。
文字はそれがもつ意味内容を把握する人の存在によって、単なる象形物以上の事物の代替としての役割を得る。(2022/7/1)
物的環境(B)の「文字情報」の表記
物的環境(B)に情報の一つの要素である文字情報も含まれるのは間違いないが、物的環境の中を分類すべきだろうか?
文字情報は物的環境の構成物の意味内容を受け取るために物質上に示された目印や手がかりのようなものであり、過去の人々が延々と物質上に刻み積み重ねてきた痕跡だ。それは横の帰りの流れ(→)の痕跡である。文字情報の本体は物的環境に含まれる。つまり物的に記号を表す存在として文字はある。よって正しく示すとすれば単に「文字」とするべきだろう。「文字情報」という表記を採用したのは意味の伝わりやすさのためだ。(2022/6/15)
「言語に基づく認知の体系」と文字情報
ヒトの脳で認知し得る世界の像は非言語的な情報も含まれるが、本論における認知の体系とはその像のうち言語で表現し得る範囲を指す。これを「言語に基づく認知の体系」と呼ぶことにする。(2020/6/18)
書籍やデジタルデータで遺された文字情報は、長い人類の歴史で築き上げられた英知の集積だ。個人によって認識される知恵や知識ではなく、言語化され文字で遺されることにより共有可能となった知識の総体を物的環境(B)における文字情報に基づく認知の体系と呼ぶ。この意味で判読不能となり失われた太古の知識は言語に基づく認知の体系には含まれない。
つまり、今運用されている知識や思想、学問の総体を包含する概念が「言語に基づく認知の体系」と言える。
近代の100年ほどで成熟した資本主義や自由民主主義の思想も文字情報が媒体となって広まり運用されている。これは現代では主流の思想の一つであるが絶対不変ではない。人の都合に合うように試行錯誤しながら構築したものだ。その本質は、本来は不安定で凶暴な自然がたまたま100年ほど安定していたという幸運な環境条件に合わせて呑気に作り上げたものに過ぎない。(2020/6/21)
物的環境(B)と言語の関わり
物的環境(B)の内的秩序が整い安定した集団内で共有された価値や事象は言語を生みだす。そして言語は物的環境において文字を生み出す元となる。
ヒトの集団で共有された物や事象に対する認知が意味内容を象徴する道具としての言語に変わり、原始の時代はその言語によって自然現象が指し示された。こうして言語は自然や神などの厳然たる変え難いものを指し示す記号として生まれ、次第に言語を表記する文字で構成された文を媒介にして学問、知恵や思想が発展した。
物的環境における文(文字)は、人が認知できる環境の様々な要素を共有するための言語の発達により大きく複雑な形に整備された。それは人の物的環境に対する働きかけの歴史と文明の発展と歩みを合わせて高度な内容を表現するものに変わってきた。
大いなる力の象徴を示す思想である宗教は、人が得られる豊かさを示す拠り所としても機能した。神に祈り神を畏れ、得られた恵みに感謝する。集団を構成する個人は大いなる神(自然)を中心に体系づけられた人的環境(F)の中に自らを位置付ける。(2020/8/5)
物の枯渇と人の協力
人類が協力して豊かな物資源を最大限に用いて素晴らしい物を生み出し利用する。
こうした協力が成り立つのは、その物が生み出す価値が魅力的で素晴らしいからであることに異論はないだろう。豊かさの象徴である便利なものや美しいもの魅力的なもの美味しい食べ物を想像してみれば分かるだろう。
これが意味することは物が枯渇すれば協力が成り立たないと言うことだ。
つまり人同士が力を合わせて価値ある物を生物的環境(C)の内的秩序へ取り込む試みは破綻する。これが現在も世界で起きている絶え間ない争いの理由だ。物が足りなくなっているのは誰もが知っている。
こうした人の営みの難しい問題に気づいたところで何にもならないのか。結局は誰かを出し抜いて物を手に入れるための方法としてしか人の知恵は機能しないのか。
こんなありふれた結論に達するから考えることに価値がないと決めつけるのではなく、その結論に至る過程こそ大事に思えるので、自分はまだ考察をやめたくない。誰もが分かる簡易な手段で強い説得力を持たせる。本論の見方とその応用の価値はあるとまだ信じられるから。(2022/6/10)
物と人の関係
人の秩序の形成過程には物が深く関わっている。この点に注目すると、縦の行きの流れ(↑)において物と深く結びついた秩序が人を強く縛り付けている構図も見えてくる。
それは人の意思と結びつき手足となった物が生み出す強い力が生み出す秩序だ。
しかし手足となったとはいえ、その物の性質の一部を意図的に引き出し利用しているだけであり、身体と同化しているわけではない。身体の性質は変わらぬまま、自然物から取り出したエネルギーや機能を利用しているのだ。
この物の特徴として、身体と同化していないので人であれば誰でも共有して利用できること、その特性の恩恵を複数人で受け取れることが挙げられる。
この人と物との関係は生涯変わることはない。所有した物であっても同化できない、一体になれないから所有をめぐる争いは終わらない。複数人で恩恵を受けられるから分配をめぐって協調が成り立つが、協調の落とし所をめぐって物と人に際限のない働きかけ(時に強制的で暴力的)がなされる。
この限りにおいて物と人は人から為されるがままに扱われている。研究され、分解され、製造の材料や燃料にされる。その物の中に人が含まれており、奴隷売買がされていた時代もある。そして物と人が結びつくことで縦の帰りの流れ(↓)において強い力で働きかけ新しい秩序を生み出した。
こうして形成された強固な内的秩序は縦の行きの流れ(↑)で人を支配する。そしてその内的秩序は際限なく働きかける相手を求め続ける。物と身体が永遠に一体にならないから、その調和を求めて内側に取り込んで秩序の境界を確定するための働きかけは永遠に終わらないのだ。
こうして「人は物にはなれない」という主旨に到達する。
物には限りがあり、いつか尽きるものだ。その時が近づくにつれて生身の人同士の価値が見直されるだろう。物は無料で限りがあり、人は有料(物や人の労力が掛かる)。しかし調和と管理は可能なのだ。この主旨は人に深い問いかけを投げ掛けている。(2022/6/21)
関連する項目
物的環境(B)に該当するA図の区分を以下に示す。
・[6] 生命成立の物的要因
・⇦7 物質的条件による制限
・⇨8 物資源の利用と消費
・(9) 物的な資産と言語による無形資産の生産と分配
・⇧10 生息環境と生物や食料の関係
・⇩41 人と他生物・人同士の生存競争力を補うため物資源に働きかける創造的行為
他の環境層の区分を以下に示す。
・自然環境(A)
・生物的環境(C)
・情報的環境(D)
・肉体環境(E)
・人的環境(F)
・心的環境(G)