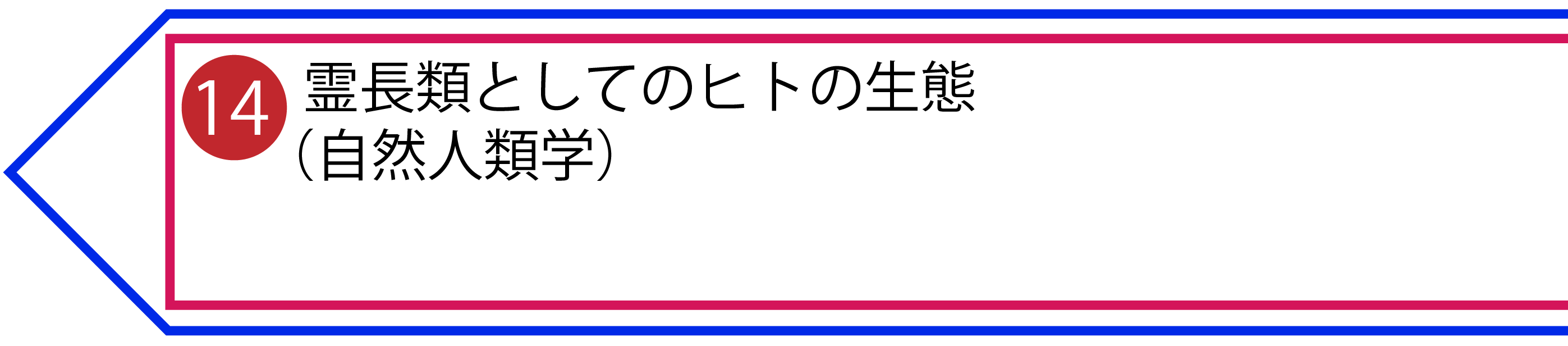
目次
- 区分(14)の定義
- 定義の注意点
- 関連する学問分野
- 区分(14)の性質
- 人の生態
- 区分(14)の形成要因
- 区分(14)の範囲の多重性
- 集団とは何か
- 区分(14)の重要性
- 区分(14)に関する考察
- 関連する項目
区分(14)の定義
生物的環境(C)の内的秩序の定義は、単に「特定の場所に存在する同一種の生物個体の集合」ではない。人同士が互いを認知して、自らと同質であると受け入れることにより結びついた複数の人の有り様が生物的環境(C)の内的秩序である。
個人が他者と結びつくことはその全てを認知して受け入れることではない。他者や既に形成された集団の中に何かしら自らに利益のある要素を読み取り、その要素に共感することで結びつく作用により維持されている。
内的秩序には当然反発する関係も含まれる。個人同士が互いに認知し合っている必要はない。個人が他者または集団に引き寄せられる作用、または自らに強制的に引きつける作用が働くことで生物的環境(C)の内的秩序は形成される。
他者の存在を許容し、自然環境下に複数の個体が存在している状態を示すのが生物的環境(C)の内的秩序だ。(2021/1/24)
区分(14)の定義の注意点
この生物的環境(C)の内的秩序という区分では、実は個人を中心とした秩序は発生していない。
祖先から両親まで繋がる命の連鎖の途中の状態を示した環境層の区分と言える。成熟して社会性を身につけた大人が、社会の競争を生き抜きながら維持している家族などの集団が存在している状態を示すのがこの区分(14)である。
繁殖して存続可能な最小の単位となるヒトの集団を対象とした学問分野は自然人類学を始めとして、現代の家族の有り様や人同士の親密な関係を対象とした研究分野など多岐にわたる。
話は変わるが本論の視野は宇宙の限界まで広げすぎて細部が完全にボヤけた突っ込みどころしか無いように思われても仕方ない部分もある。しかし何とか要旨だけを受け取って貰い、その突っ込みを生かして人それぞれに詳細な内容を明かすための基礎的な枠組みの一つになれば良いと思う。(2022/11/22)
関連する学問分野
生物的環境(C)の内的秩序の区分(14)は、生物種としてのヒトが獲物を得たり繁殖したり存続をするための生態や集団行動を対象とした学問分野が当てはまる。
[wikiより「自然人類学」とは、人類やチンパンジーやゴリラなどヒト科の共通祖先からどのように現生人類が進化してきたのかを解明する学問]
(2022/11/26)
区分(14)の性質
生物的環境(C)の内的秩序である区分(14)は人の生物的な特性に基づく行動の様態を示す。
これは物や道具を用いない生身の生物としての人の生態に基づく生物間の関係の有り様を示す区分だ。生態の主なものとして繁殖行動や捕食行動が挙げられる。
捕らえられて食料として保管されている生物もこの生物的環境(C)の内的秩序に含まれる。これは内外の境界を示す重要なポイントだ。
生物的環境(C)の外的環境は食料となる生物をはじめとした周囲に存在する生態系の生物全てを指す。
そして物的環境(B)に見られる物資源や道具を用いた行動は、この区分(14)の人の基礎的な生態の延長や派生として現れる。(2022/10/8)
区分(14)と人の生態
身体を持つ生物個体は活動する。その身体を維持するための食料を得ながら。
生存可能性を高めるためには、食料をより多く、確実に得て、家族を増やす繁殖行動をして、外敵から身を守る行動をする必要がある。
元々自然環境は様々な動植物がひしめき競争し合っている世界だ。
その中で人という生物種が他の生物種に対して優位を保ち生存、繁殖、存続するためには集団の大きさで競争力を高めることが有益な手段となる。
集団が大きいほど強い力で他生物を制圧できるし、組織的に協力することで多様な作用を環境に及ぼし、自然環境にある物資源を活用して生産物を生み出すこともできる。
このような個人を中心とした集団の有り様を示すのが生物的環境の内的秩序だ。言い換えると身近な人同士の関係性で成り立つ区分だ。
この区分(14)の要素が行動に与える影響は非常に大きい。(2020/7/23)
区分(14)の形成要因
生物的環境(C)の内的秩序は利害の一致した人間同士が集団を作り行動を共にすることにより成立する。その集団を支えるのは同じ地域に住み、同じ狩場から食糧を得るために、一緒になっているなどといった条件だ。ヒトという生物種にとって仲間と分け合うのは当然の前提となっているようだ。
利害の一致した集団内では、争ったり殺し合うことはない。集団の成員同士が関係を維持するのに大きなコストはかからないのだ。何らかの理由で内部分裂したり、他の集団とぶつかった時に初めて、その関係を取り持ったり、均衡を破るために物資や道具に頼る。貢物や武器、これが物資源の利用の始まりであり、物的環境(B)の内的秩序の発達の始まりだ。(2020/7/24)
区分(14)の範囲の多重性
生物的環境(C)の内的秩序は周囲にいる人、家族や大事な人が存在している状態を示す。
人の遺伝子を持った他の個体が存在する状態は、ヒトの遺伝子を持つ個体のコピーが複数存在することを意味する。これが生物的環境の内的秩序の定義であるが、個体の差異を識別するコードが多数ある社会の現状(つまり多様な人々が居ること)を説明するには余りに単純すぎる。
社会の秩序を機能させる人間関係は無数に存在し重なり合っている。その可能性を包含した人間群が生物的環境の内的秩序であると定義づけるべきだろう。(2022/6/17)
集団とは何か
複数の個体による行動の同期または行動の同質性が集団を形成する条件だ。
もう少し詳しく述べると、同じ行動だけではなく共有する価値観や利益、作用に基づいて複数の個人が行動したり、環境において複数人に行動を促す要因が発生した場合も集団を生み出す。
そして大事な点として、基本的に行動の発現によって集団は維持されることを押さえたい。つまり集団とは生物的環境の内的秩序の状態を意味するのではなく、その状態を背景とした行動の結果を示す概念と言えるかも知れない。(2021/1/26)
区分(14)の重要性
人の個体は生物として一つのまとまった機能を持って個別に存在している。
これに対して生物的環境(C)の内的秩序は複数の個体が活動する、人の営みの中心的な環境要素だ。行きと帰りの流れ双方において個人に多大な影響を及ぼす区分だ。
人は世界に無秩序に存在しているわけではない。長い年月をかけた行きと帰りの流れ双方の影響が積み重なった上で今のようになっている。複数の人同士の関わりは行動の基礎的な要因となり、行動は人に対してなされる。この区分が人の行動の重要な要因であることに疑いはないだろう。(2021/1/26)
区分(14)に関わる考察
生物的環境(C)の内的秩序が繁殖と存続に十分な状態に達すると、集団の拡大に向けて人数が増加を始める。
これが情報的環境(D)の横の行きの流れ(←)の起点[16]となる。繁殖能力の程度により個体数が変わり、それに伴い集団の有り様も変わって行く。最小の単位である母子は集団というには少人数であるが、これが起点となる。ここで一個体の成立を意味する環境層の情報的環境(D)の定義を改めて確認したい。
家族という集団に父親が加わったり、親族の集団や集落が築かれる過程の説明は人類学に譲るが概ね人口は増加の一途を辿った。
自然環境との戦いの中で生存を勝ち取ることは生物の宿命であり、人も同様だ。自然環境に対して優利な戦略は生物種によって様々であるが、人は個体を集合させることで生存の力を得ようとした。生存は他生物の脅威を回避して、他生物を捕らえて摂取することにより成り立つ。競り勝つための力を集団を形成することによって得たと言える。
ここで、どこまでが「行き」の流れなのかという疑問が浮かぶ。「行き」の流れは個人の意思とは関わりなく自然に影響を及ぼす関係性を示すものであり、能動的な行動として示される「帰り」の流れとは違う。
はっきり言えば横の行きの流れ(←)は時間の流れだ。人の望む意思とは関係なしに流れる大きくて強い力の流れである。そして人の意思も時間の流れと無関係では無い。
どこまでが人の意思で、どこまでが逆らいようの無い時間の流れの力かという線引きはできるのだろうか。これを判断するには脳の働きを基準とするのが妥当だろう。人の営みの元となる環境による縦の行きの流れ(↑)である刺激を受け取って縦の帰りの流れ(↓)である行動という反応に至る結節点が脳の働きだ。
しかし実際には「行き」にも「帰り」にも脳の働きは関わる。認知が「行き」であり、その認知をきっかけとして行動に至る脳の働きは「帰り」だと言える。
これを繁殖に当てはめると、異性を認知して様々な手段を講じて性行為に至ることは「帰り」だが、子を受胎して出産することは「行き」の流れだ。ここでいう認知とは言語で表されない無意識も含む。そのため言語を生み出す前の人類にも当てはめることが可能だ。
繁殖の結果として人口が増えるのは「行き」の流れであると上に述べたとおりで、この結果現れる複数個体の集合が生物的環境(C)の内的秩序だ。
人の集団に関わる事象は、それが人の営みの全てに思えるほど広い学問領域をカバーする。これは人が社会的な生物だからだ。
しかし、生物的環境(C)でその全てを説明できるわけではない。この区分では物資源を利用した経済活動の有り様を除いた生物としての人の有り様が示されるのみだ。述べられるのは自然環境の元に生物個体が発生し、繁殖が繰り返された結果集団となるところまで。
社会システムと言われる人が作り出した社会構造の働きは全て「帰り」の流れに含まれる。だが、「行き」の流れにおける人の繁殖能力は人の営みに関わる問題全ての根源と言えるほど重要だ。
ここで「行き」と「帰り」を分けて分析することに意味はあるのかという疑問は避けられない。
人間が様々な行動により存続の道を切り開いてきたことが事実であるなら、それだけを注視すれば良いのでは無いか。なぜ、「行き」だけを分離するのか。もともとこの二つは実態として一体になって作用するものであり、「行き」の概念は環境要素として想定しただけのものだ。
しかしその大きな影響力を考えると無視はできないのだ。
生物的環境(C)の内的秩序は「帰り」の流れによって何度も人の手が加えられ変化しながら「行き」の流れによって膨張を続けた。それは直接的には農業革命による食料の増産の影響であったり、間接的には政治的な影響だ。
以上、回りくどい説明になってしまったが端的に「人が色々やった(↓)結果として、その繁殖能力(↑)の爆発により人口が増えた」と述べるに留めるべきか。(2020/7/21)
関連する項目
(14)に関連のある42区分を以下に示す。
・⇧15 個人の誕生と発達の背景
・⇨13 家族集団による生存活動
(14)に関連のある用語について述べたページを以下に示す。
・生物的環境(C)
・内的秩序
考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。
・4つの流れ理論
