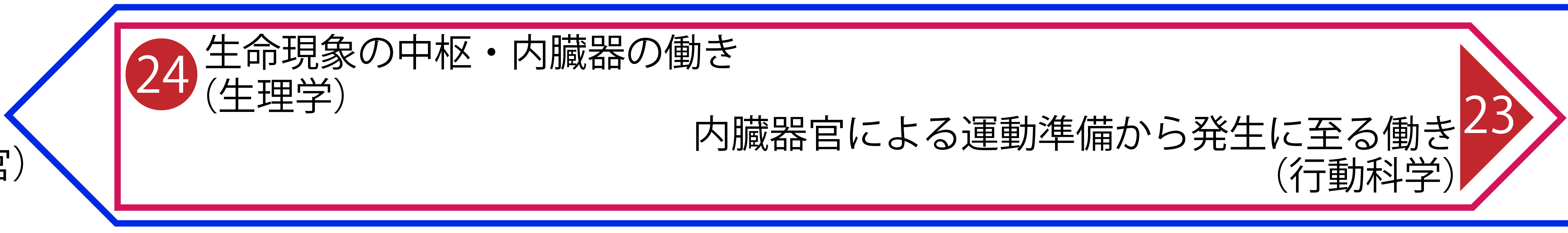
目次
- 区分⇨23の概要
- 区分⇨23の定義・関連する学問分野
- 肉体環境(E)の内と外の役割関係について
- 区分⇨23の生存可能性に関わる働き
- 行動パターンと区分⇨23の関係
- 他生物と比べて突出した働きとしての区分⇨23
- 関連する項目
区分⇨23の概要
内臓器官と脳や神経系を通じて感覚器や運動器官を動かす信号、中でも自律神経系(無意識)の働きによって起こる信号について対象とした学問分野がこの区分⇨23に該当する。
そして意識的な行動に関わる内臓器官の働きも、区別する必要はあるが同じ区分⇨23になる。
以上の2つの重要な性質が明確に表れているのがこの区分⇨23であると言える。この2つの性質を分けるのは縦の帰りの流れ(↓)、つまり脳の働きである人的環境(F)の影響を受けた内臓器官の働きかどうかだ。(2022/11/22)
区分⇨23の定義・関連する学問分野
肉体環境(E)の内的秩序から外的環境に向けた流れの区分⇨23は、内臓器官の統合的な働きにより行動が発現する直前の過程を示すものであるが、行動に至らない身体維持の働きも含めて身体制御の働き全般が該当する。
[wikiより「行動科学」とは、人間の行動を科学的に研究し、その法則性を解明しようとする学問。心理学、人類学、精神医学などがこれに含まれる](2022/11/26)
肉体環境(E)の内と外の役割関係について
外部からの感覚刺激による情報に対して、身体の臓器を守る行動をするための認知の統合や制御が脳で起こるのだが、もう少し肉体環境(E)を分析しよう。
時間に伴う変化の流れの中にあって自律的に制御するための空間(臓器)を身体内に設けているのと同時に、制御できない外の現象との出入り口(境界)をうまく制御しなければ、自律性は侵されて破壊されてしまう。
身体内の機能としての外と内の出入り口(境界)の制御に関するもの。これが肉体環境(E)の外的環境(感覚器と運動器官)の役割である。
情報的環境(D)の外的環境との違いについても補足として述べる。
情報的環境(D)が身体構造の全てを司る生命分子の働きを一括りにした内的秩序と、それ以外の身体に関わる外の物質(外的環境)という区分であるのに対して、肉体環境(E)の外的環境は身体器官の区分として定義されている。(2022/7/11)
区分⇨23の生存可能性に関わる働き
原始時代の人はライオンなどの敵を目で見て認識した上で、自由に運動できる身体を用いて襲われそうな場所を避ける行動を取ることによって生存可能性を高めた。(2020/7/24)
行動パターンと区分⇨23の関係
行動パターンとは、身体を用いて周囲の離れた対象に働きかけるための一連の制御プログラムと言える。
それが起動すれば身体は実際に行動を起こすことになる。五感を働かせて手足を動かして行動の目的に近づける。現代人においては行動パターンは言語や道具も駆使したものとして現れる。
離れた対象に働きかけて目的を達成するための行動パターンは、個人の発達過程における成功体験によって形成される。それには道具の使い方を覚えたり、物を指し示す記号の一つで物や事象の代替となる言語を駆使した体験も含まれる。(2022/7/16)
他生物と比べて突出した働きとしての区分⇨23
人は食べ物を摂取して身体を作ったり運動するために栄養を消費する。
進化の過程で他生物に比べて栄養を消費する量が多くなったのが脳だ。肉体環境(E)の中にあるこの脳という部位はどんな働きをしたか。
無作為の身体運動が放散的に起こるのではなく、感覚器官から受け取る刺激を整理して、まとまった反応として行動に反映させることができるのは脳の働きによる。
この働きは「豊かな環境認知」能力と呼べる。この認知力と情報整理の質と量によって人はライオンやゴリラに比べて限られた小さな力であっても適切に環境に対して力を及ぼすことを可能にした。
人は、行動という形で余剰エネルギーを自然環境に向けて放出する際の、環境の状況に応じた行動が他の生物に比べて秀でているのだ。それを可能としたのが認知能力だ。(正しくは身体能力の高さではなく、手先で物に働きかける能力の高さを基礎にした認知精度の高さが他生物を出し抜く行動を生み出していると言えるだろう)
生態系において多くの生物がいる中で最も環境認知と感覚情報の整理統合の機能が高かった人は、判断の的確さで他の生物を出し抜けたのだ。
それは人にとって都合の良い力の行使を意味し、更なる力の余剰を生み出すことになった。(2020/7/24)
関連する項目
⇨23に関連のある42区分を以下に示す。
・(24) 生命現象の中枢・内臓器官の働き
・⇦22 身体を通じた心理作用
⇨23に関連のある用語について述べたページを以下に示す。
・肉体環境(E)
・横の帰りの流れ(→)
・内的秩序
考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。
・4つの流れ理論
