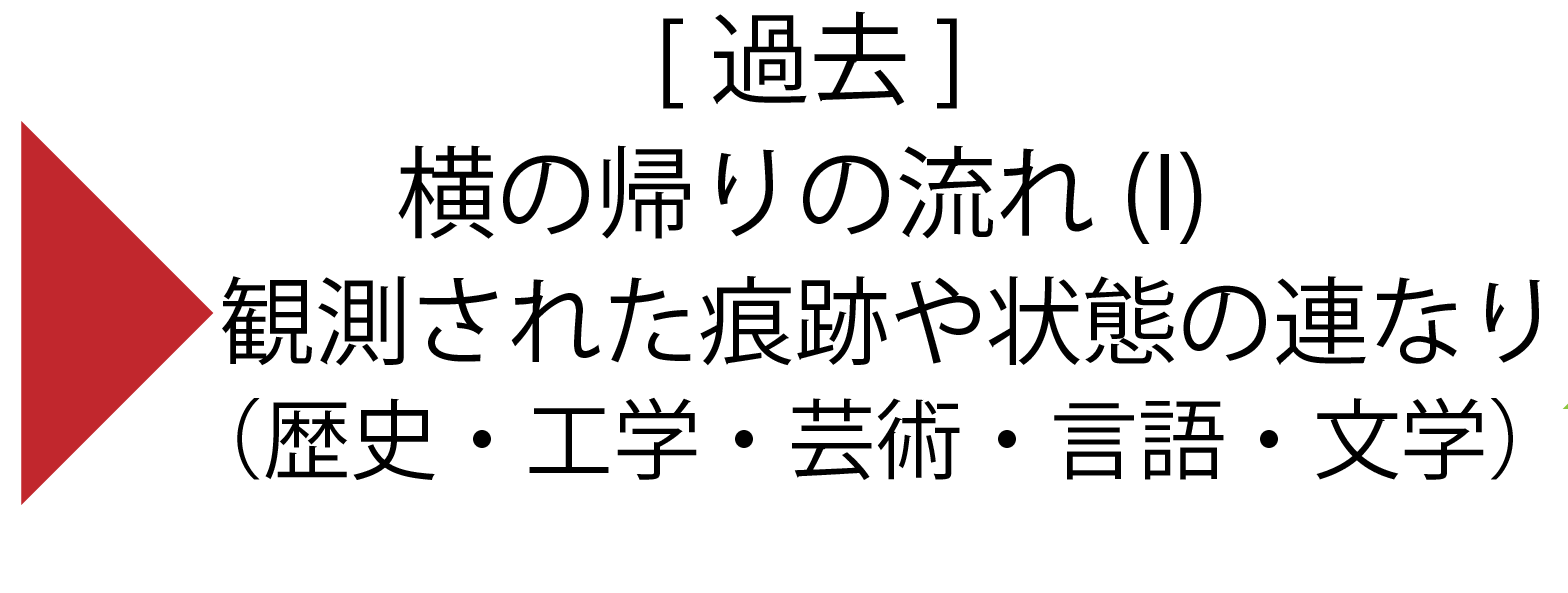
目次
- 横の帰りの流れ(→)という概念について
- 横の帰りの流れ(→)の現れ方に関する大事な補足
- 横の帰りの流れ(→)の2つの様態
- 横の”帰り”の流れという表記について
- 横の帰りの流れ(→)の自律的な働き
- 縦の行きの流れ(↑)を推進する横の帰りの流れ(→)
- 生命のあり方の本体としての横の帰りの流れ(→)
- 行動による横の帰りの流れの痕跡と横の行きの流れ
- 横の帰りの流れ(→)と歴史
- 横の帰りの流れ(→)の結果としての創造物
- 個人の意識が受け取る縦の行きの流れ(↑)の正体
- 環境層ごとのせめぎ合いについて
- 現在を記述するための大きな2つの要素
- 環境層の行きと帰りの流れの関わり
- 横の流れの行きと帰りの合成
- 横の帰りの流れ(→)の強さの現れ
- 自己形成の仕組みを4つの流れで捉える
- 考察
- 人工物と自然物
- 横の行きの流れ(←)の中にある横の帰りの流れ(→)
- 関連する項目
横の帰りの流れ(→)という概念について
ある一時点における各環境層の状態を意味するのが横の帰りの流れ(→)だ。
これは過去から未来へ向かう時間の流れの中で、その時点で保たれている状態と結果を意味する。縦と横の帰りの流れの結果として維持された「状態」を指すのを「流れ」と呼ぶのは違和感がありそうだが、時の流れに対する概念としてこのように呼ぶ。
これは一時点の状態を指す概念であることから流れと呼ぶのは厳密には正しくないが、この状態は常に縦と横の帰りの流れによって変化の圧力を受けて書き換えられているので、時間の流れを意味する横の行きの流れ(←)に反する流れという意味で呼んでいる。(2021/1/28)
横の帰りの流れ(→)は横の行きの流れ(←)の結果として維持されている一時点における各環境層の状態を意味する。
この状態は一定時間内に与えられた縦と横の帰りの流れの影響も含まれたリザルト的なものと言える。(2021/2/12)
横の帰りの流れ(→)は自律的に維持される環境条件と、それに加わった人の行動の影響を受けた環境条件という二つの意味を兼ねている。
一時点における各環境層の状態を示すのに、自律的な働きによるものか人為的な影響によるものかを区別することは意味を持たない。
どちらも同じ時間の流れの中で維持される生命の有り様であることに変わりはないからだ。(2021/2/12)
横の帰りの流れ(→)の現れ方に関する大事な補足
時の流れを「←」と示して、人が存続し続けた営みの軌跡(歴史)を「→」とする定義について重要な補足。
人は集団の秩序を築き助け合う一方で、同士の争いも絶えず行われていることから、実際には←に対する→というシンプルな構図には到底なり得ない。
概ね→の方向を向いた多数の個人や集団が衝突を繰り返しながら、次第に強い流れに小さな流れが淘汰され飲み込まれながら、あるいは小さな流れを包摂しながら全体的には→へ進んでいると考えるのが正しい捉え方だ。(2022/9/26)
横の帰りの流れ(→)の2つの様態
横の行きの流れ(←)は各環境層が内包する複数の秩序間のせめぎ合いと緊張を起こす要因となる。
この横の行きの流れ(←)に対する帰りの流れ(→)とは環境要素の状態のみを示す概念である。実際に発生する衝突やせめぎ合いは時間の経過に伴う、各物質の物理的特性の違い(質量や流動性)から起こるズレに起因する。
そして、自然環境(A)~心的環境(G)の環境層はそれぞれ時間に伴う変動のスケールが全く違う。これは各層の物理特性の違いによって起こる。
この違いを一つの小さな構造で受け止めるのが物質の集まりの一つである生物であり、その反応である。この反応は⑴認知的反応と⑵物質的反応に分類される。
⑴認知的反応とは、そのずれの状況を身体の感覚器で受け取り(縦の行きの流れ)行動として発現させること(縦の帰りの流れ)だ。
この受け取る情報は基本的な認知力に頼る全ての情報と言える。自然物の形、色、性質の違いを五感で受け取るという普段人が当たり前に行うことだ。そして受け取る時間や感覚の程度は環境層ごとに異なる。こうして人生上の様々な体験が縦の行きの流れ(↑)に影響する。
厳密には心理学に説明を譲ることになるが、ここで言う縦の行きの流れ(↑)は非常に広い範囲の環境条件から見た行動に影響を与える要素という意味で定義している。
以上のような縦の行きの流れ(↑)に関わる反応が認知的反応だ。
⑵物質的反応とは、感覚器を通した認知を介することなく、結果として横の行きの流れ(←)に対して身体を維持する結果を残せた状態を示す横の帰りの流れ(→)を意味する。
無意識の自律的な内的秩序の働きが関わっている。具体的には生命の基礎的機能である環境条件と隔離された身体の内臓器官を維持運用する働きや重力に対して直立することなど。
この意味で横の帰りの流れ(→)は行動と自律神経の2つの要因によって維持されていると言える。(2021/2/3)
横の”帰り”の流れという表記について
横の帰りの流れ(→)について。
時間の流れを意味する横の行きの流れ(←)は一方向にしか進まないのに「帰り」があるとは不可解な表現に思われるだろう。これは文字通りの意味ではなく縦の帰りの流れ(↓)に対応した表現であることに注意してほしい。
横の帰りの流れ(→)は縦の帰りの流れ(↓)の影響が時間に伴い堆積してゆく過程を追う流れである。
この流れは横の行きの流れ(←)と共に時間に伴い変化してゆく点では変わらない。
ところで人以外の生物も自然環境と関わりながら影響を与え続けている。その影響も環境に残り続ける点に変わりはないが、そのような関わりは生態系の基本的な仕組みであり、あえて行きと帰りに分けて考えることに意味がないほど複雑に溶け込んだ過程である。
本論文であえて帰りの流れとして取り上げるのは人の本質に迫る必要があったからだ。帰りの流れとはそうした特異な概念である。(2021/9/5)
帰りの流れは生物的な特性である環境条件に対する反射を示すものだ。
これが縦の帰りの流れ(↓)で、その流れの影響が環境要素(各環境層の外的環境)に到達して変化を及ぼした状態とその前の時間の状態の差によって現れる流れが横の帰りの流れ(→)である。
文脈によって横の帰りの流れ(→)と縦の帰りの流れ(↓)の合成として行動の影響と記述している箇所があるが同じ意味だ。(2021/4/23)
横の帰りの流れ(→)の自律的な働き
個人の意識へ向けて環境の影響が統合してゆく過程(縦の行きの流れ)を通して、経験が心的環境(脳)に蓄積される点は押さえたい。
体験が心的環境(G)の内的秩序の形成に影響する。この体験とは行動に関連するものだけではない。
各層の「行動を介さない内的秩序の運用」(睡眠時の代謝作用など自律的で無意識の作用)を横の帰りの流れ(→)と定義することになりそうだ。横の行きの流れ(←)に伴う自律的な現象としての内的秩序の運用が横の帰りの流れ(→)であると。
この意味で横の帰りの流れ(→)は、意識的な行動によるものと身体の自律的な働きによるものの両義的な性質を持つことが示される。
このように考えると、従来の横の帰りの流れ(→)の定義である「人が環境層に与える影響の積み重ね」の要素は「行動を介さない内的秩序の運用」を含めた合成物であることを意味することになる。これは妥当に思える。
そして、その横の帰りの流れ(→)は外的環境の流れの中に存在する。
人は自然物と人工物の合成された環境の中で無意識の作用と意識的な行動を合成させながら生きている。普段はそれらの要素を区別せず、利用できるものを随時必要に応じて受け取っているだけだ。
時間が経てば意志に関わらず腹が減るのも、それを解消するために食事という行動をするのも経験として心的環境(G)に溜まってゆく。むしろ横の帰りの流れ(→)が行動の原理と言ってもよいほどの縦の行きの流れ(↑)を発生させているのだ。食事は代表的な例だ。
横の帰りの流れ(→)の働きが縦の行きの流れ(↑)の発生する要因であることが分かった。人の生の本質に迫る非常に重要なポイントなので必ず押さえたい。(2022/6/22)
縦の行きの流れ(↑)を推進する横の帰りの流れ(→)
実際の現象には縦の行きの流れ(↑)が心理過程を意味し、横の帰りの流れ(→)が自律的な生命活動の過程であるという明確な区分は無いのだろう。
←も→も↑も混じりあって一つの現象となっている。
←に対する→は生体の主要な働きであり↑↓は派生的な現象である。
→において←との境界で何が起こっているか?各環境層で→←のせめぎ合いがある。例えば身体にはそのせめぎ合いを感知して解消するための行動につなげる仕組みがあるはず。それが↑であり生物に概ね共通する働きによって現れる。
自然環境(A)では→←は気温と体温のせめぎ合いとして現れる。体内を常温に保つ働きは意識や行為と直接は関わらないが↑の経路は使われる。これが無意識の働きだ。
自律神経系の働きで常温が保たれる。この働きを意味する→は一時点の状態を示す概念と言える。→から派生する自律的に生命を維持する構造は↑で示される。
→は←との一時点の関わりの境界の状態を示すものであり、生体活動の↑(代謝や呼吸などの作用も含む)を取り除いた物質的な位置関係のみを示す。
これは考察初期に→を歴史の積み重ねのあり方であると定義した内容と一致するので妥当な定義だ。この定義に身体の状態も加わったものといえる。
ということは、行動に至らないが↑の心的環境(G)まで至る作用を自律的なものと捉えることになる。
体温が正常で身体が物質的に外的環境と隔てられており、かつ外界と身体の境界の一つである口を通して取り入れた食料が身体内に存在し、なおかつ、外から取り込んだ食料の栄養素が適切に働いている。ここまでが生命活動を維持する基礎である。
←の中に→があるという物質的な状態から←の進行に伴って→とのせめぎ合いが発生し、それが↑と↓を発生させるということ。
4つの流れの関係はこれが最終解だと思う。だが詳細を記述して証明できるかは不明だ。(2022/7/7)
生命のあり方の本体としての横の帰りの流れ(→)
縦の行きの流れ(↑)は行動に至るエネルギーの流れの特徴を構造から明らかにしたものだ。情報ではなくエネルギーとしたのは、より広い流れの概念を含むからだ。この意味で情報もエネルギーの流れの一種である。
自然環境の中に生きる人という生物が行動という特徴的な現象を起こすに至る仕組みを説明する。
エネルギーの流れは縦の行きの流れ(↑)において各環境層を経て意識となり、その意識は身体の統合的な働きである行動を起こす。
この前提として生存していることが必要だ。縦の行きと帰りの流れは、横の行きの流れ(←)に対する横の帰りの流れ(→)、生命活動の派生として現れるからだ。
生きて覚醒している状態においてのみ起こる現象が行動である。
そのため人の生の本流は横の行きの流れ(←)に対する帰りの流れ(→)であると言える。
横の帰りの流れ(→)は無意識も睡眠状態も含めて、個人が時間の流れの中で生を維持している状態を示すものだ。縦の行きの流れ(↑)はそれと関わり、派生したものだ。
では横の帰りの流れ(→)とは何か?
横の行きの流れ(←)に対する横の帰りの流れ(→)という概念は、環境を構成する自然物(←)も個人の身体(→)も共に、自然法則に倣いながら異なる系を維持している関係性を示したものだ。
しかし実際には二つの流れの境は常に開かれており(呼吸する口とか)外の環境状況と深く関わっている。
その関わりの有り様は縦の行きの流れ(↑)として現れる。では各環境層でどのように内と外で分かれながら関わりを示しているのか?
生命に特有のエネルギーの流れの系が自然環境(A)の中で維持されていることを示すのが横の帰りの流れ(→)であり、その境界の関連の詳細なありようを示すのが縦の行きの流れ(↑)であると言えそうだ。→と↑の両者が密接に関わっている。(2022/7/5)
横の帰りの流れ(→)と縦の行きの流れ(↑)の違いは行動に至らない経路と至る経路である。
横の帰りの流れ(→)は常に働き続けており、横の行きの流れ(←)との関わりによって状況は常に変わり続ける。
それを随時、行動に向けてエネルギーを統制して集約する仕組みが縦の行きの流れ(↑)なのだ。よって常態の横の帰りの流れ(→)も明かす必要がある。
主に自律神経の働きによって維持される身体の有り様が横の帰りの流れ(→)の正体と言えよう。(2022/7/5)
行動による横の帰りの流れの痕跡と横の行きの流れ
人が死んでも人工物は遺り続けるが、その場に人が生きて存在して人工物の意味を見出すことで初めてそれは機能する。
自然物を加工して何かを作り出せば不可逆的にそれは人工物であり続け、元の自然物に戻ることはない。
人が作り出した物や自然に残した痕跡は、風化して人工物としての判別が不可能になることはあっても、物理的に与えた変化は形を変えながら恒久的に引き継がれるものだ。
そして数少ない手を加えられていない自然もまた、現代に引き継がれ、人はその恩恵を受け続けている。
そして、連綿と引き継がれる言語・思想も書物や機械や慣習によって引き継がれている。
この意味で横の行きと帰りの流れは一体である。
横の帰りの流れ(→)の人工物と横の行きの流れ(←)の自然物の区別は可能であるが人にとって欠かせないものとして同様の価値を持つ。(2022/6/8)
横の帰りの流れ(→)と歴史
横の帰りの流れ(→)は人の行動の結果の積み重ねの軌跡を辿る視点であることから人類史の視野が適している。
しかし歴史という括りは大きすぎるのでもう少し視野を特定して、各環境要素が人の営みに伴ってどの様な変化をしてきたかを歴史的視点で捉える。
あるいは私達が認識する日常の出来事そのものがこの横の帰りの流れ(→)と言って良いか。その集合が歴史の流れを作る訳だし。(2021/10/10)
横の帰りの流れ(→)の結果としての創造物
横の帰りの流れ(→)としての言語(文字)について述べる。
これは創造物、創作物、芸術などの表現物、人の営みの全般にまで範囲を広げて言えることだ。
人の創造物のどれもが人の行動(↓)によって生み出されて、残った(→)ものであり、未来(←)における人の営みに影響する内的秩序(↑)を形成する。これは4つの流れについての包括的な記述だ。
これは4つの流れ理論を説得の根拠、説明の手段として伝えたいことの一つだ。(2022/8/10)
個人の意識が受け取る縦の行きの流れ(↑)の正体
横の行きの流れ(←)により内外の強い摩擦が生まれ、その状況を縦の行きの流れ(↑)で個人の意識が受け取る。
そして、縦の帰りの流れ(↓)と横の帰りの流れ(→)で力を行使してその摩擦に対処する。摩擦に直接働きかけることもあれば他の優位な条件を生かすことで間接的に対処することもある。
結果として現れた新たな横の帰りの流れ(→)が積み重なってゆく。
この意味で横の帰りの流れ(→)は一時点の環境要素の物理的な状態を示すものであり、縦の行きの流れ(↑)はその物理的状況を認知により統合的に受け取る過程を示すものと言える。
それでも横の行きの流れ(←)は止まることなく内外の隙間を埋める圧力を生み出し、摩擦や関係の綻びを炙り出し、縦の行きの流れ(↑)でそれを受け取り、対処する行動が起こる。この繰り返しだ。(2021/3/1)
環境層ごとのせめぎ合いについて
各環境層ごとに異なるせめぎ合いと緊張があり、その全てが悩みと争いと問題の元になっている。
個人が存在する時点や場所により、最大の関心ごとの中心となる環境層は異なる。
しかし個人にとって全ての環境層が内外の隙間なく空間を埋める物質間のバランスによって構成されている点は変わらない。
この状態は長い時間をかけた縦の帰りの流れ(↓)の積み重ねである文明と個人的な経験により維持されている。
横の行きの流れ(←)に対して、縦の帰りの流れ(↓)によって働きかけることで横の帰りの流れ(→)を維持しようとするが、横の行きの流れ(←)の力が大きいのに対して縦の帰りの流れ(↓)の力によって押し留める力は強くはない。
ただ、縦の帰りの流れ(↓)は縦の行きの流れ(↑)で得られた認知を集団的な統率のとれた大きな力(文明の力)に変えることによって強さを増している。
この集団の秩序に基づく強さの秘密にも迫る必要がある。
横の行きの流れ(←)の自然状態の中に、人工物が張り巡らされた現代社会は、人工物によって機能の分割と統制がなされ、その人工物に対して認知を重ねて生み出した価値を示す文字情報(貨幣)の移動と取引も実現している。
この横の行きの流れ(←)から縦の行きの流れ(↑)が生まれて、集団的認知に基づいた縦の帰りの流れ(↓)の行動に発展させるメカニズムも具体的な記述をしたい。
特に現代文明の最先端である情報技術の位置付け、文字情報と物的環境の定義づけによる区別。詳細な現象の分析について。(2021/2/3)
現在を記述するための大きな2つの要素
人の長い長い歴史の中で様々な問題と向き合った結果として現在がある。
4つの流れの行きと帰りだけで複雑な絡み合いを明かすなど不可能に思える。
だが最も単純に整理するためには、横の行きの流れ(←)に対する横の帰りの流れ(→)が今どのようになっているのかに着目するのが近道だろう。
つまり、各環境層の外的環境を示す横の行きの流れ(←)に対し、内的秩序である横の帰りの流れ(→)は今どんな方策、システムで支え、秩序を形成しているのかを明かすのだ。
縦の行きの流れ(↑)は長い時間をかけて積み重なった環境層を基準に現れる流れだ。環境層同士は因果関係を持ちながら下の層から順に積み上がっている。
横の行きの流れ(←)と横の帰りの流れ(→)はせめぎ合い、釣り合って現在の瞬間を構成している。その現在に働きかける縦の帰りの流れ(↓)は徐々に積み重なって、新たな縦の行きの流れ(↑)を形成する環境層を長い期間をかけて作り上げてゆく。
横の行きの流れ(←)と横の帰りの流れ(→)のせめぎ合いとは何か。
横の帰りの流れ(→)は人が作り上げた過去から続く仕組みや集団が、その瞬間にどの程度保たれているかの状態を示す概念だ。(2021/2/1)
環境層の行きと帰りの流れの関わり
環境層の行動への関わり方は「行き」の流れと「帰り」の流れで全く違う。
行きでは行動の土台として関わり、帰りでは行動に対する強い抵抗力として働く。
そして、個人が環境に対する反射である行動をなし得るのは寿命分のわずかな期間しかないのに対して、個人に影響を与える要因である各環境層は遠い過去から未来へ連なる時間軸の中に存在する。
この両要素は別々に解析しなければ本質は見えない。(2020/8/5)
横の流れの行きと帰りの合成
環境要素は自然物と人工物の混合体である。
長い歴史を通じてこの枠組みは作られてきた。それは各環境層において必要なものを内的秩序に取り込み制御する試みの積み重ねであったと言える。
自然環境に生身の身体で対峙していた太古の状態から、人は様々な事象と事物に働きかけを続け、制御可能な内的秩序に取り込むことで生存を実現させてきた。
その積み重ねが人類の歴史であった。
何が内的秩序で何が外的環境かと言う認識は身体とそれ以外で分けられるほど単純ではない。野生動物であってもそこまで単純な認識では生存して存続はできないだろう。
内外の広さを示す範囲もその境界もとても曖昧で、人について言えばその時代ごとの価値観やその土地の文化や思想にも影響を受け現在に至るまで変化をし続けている。
長い歴史を通じて変わらないのは、可変的な内外の認識は絶えず「内的秩序から外的環境への働きかけ」を促す根拠となってきたことだ。
人は他の生物と同様に、生存する限り絶えず行動を通じて外的環境に働きかけ続ける。そして働きかけを通じて外の事象を内的秩序へ取り込もうと(自分に都合の良い作用を促そうと)し続ける。
これが縦の行き(↑)と帰り(↓)の流れと横の帰り(→)の流れだ。
愛情や信頼関係に基づく人同士のつながりが両者を互いの内的秩序へ取り込んだり、大きな人類愛が実現して全ての人間関係を内的秩序へ取り込めたらと言う仮定は無意味だ。
人は全ての人間を内的秩序へ取り込みたいとは考えず、身近にいる優良な個体(異性)との関係を深め、内的秩序に取り込もうとするものだ。
他者は別個体であり、身体の境界を越えられないという実感と体験に裏付けられた価値観しか持ち得ないのだ。互いが相手をどのように内的秩序に取り込んで認識しているか(互いをどう思っているか)を知ろうとする努力はできるが、それを裏付ける根拠は本人でさえ示せないだろう。
しかし、物理的な合理性によって成立する科学を始めとした文明の力によって人は協力して物を内的秩序に取り込むことを実現してきた。
そこに価値のある物があったから、それを手に入れるために他の人間を利用して、互いに利益が一致したから両者は生かされたのだ。(2022/6/10)
横の帰りの流れ(→)の強さの現れ
本来ヒトの個体の行動による自然環境への影響は微々たるものであった。
そして現代においても一個人の持つ腕力は変わらないが、自然環境に影響を与えるほどの大きな力を行使するようになったのは、集団によって認知を共有する能力によって実現した文明の力を得てからだ。
その力の有り様を理解するためには、個人が関わり取り扱える力の強さと余剰エネルギーの増加が大事な視点となる。他者と異なる役割を持った行動を、同一の目的へ向けて同期することで組織的な強い力を生み出すことを覚えたヒトは、環境に対し強い力を発揮するようになった。
このように人が環境に及ぼした影響は加工された環境要素として遺され、次の世代に引き継がれる。次の世代はこれを土台として更に影響を積み重ねる。
この繰り返しによって文明は発展してきたのだ。(2020/8/5)
自己形成の仕組みを4つの流れで捉える
人が生まれたばかりの状態から無秩序に周囲の刺激を受け取る過程を重ねる中で、自分を知ったりさまざまな知識を得る過程を大雑把に説明する。
それは構造的に引き算をして自己を自然環境(A)から削り出してくる仕組み(環境層の段階)と、経験的に引き算をする仕組み(内と外の状況により境界を確定してゆく)の2つの仕組みを通して自分とその周囲の世界の境界を心的環境(G)に蓄えてゆく過程である。
周囲状況と経験知識を照らし合わせて行動を決める。これは誰もが普段行っている心理過程だ。
常に周囲状況のフィードバックを受けながら経験・知識・記憶に基づく内的秩序(①行動の内容・②その行動によって働きかける対象・③その結果として期待できる効果・3つの情報で形成された行動パターン)に従って行動する。(2022/6/23)
横の帰りの流れ(→)の総合的な考察
人が身体の健康を保ち生存するために必要な行動(生存に適した気温や湿度の状態を得るための身体移動)から始めて、次に食料を安定的に得るための働きかけ(生物的環境)を行うといった風に、各環境層における外的環境に対して人為的な働きかけを環境層の上の層(心的環境)から順に行なうこと。
これが、横の帰りの流れ(→)である。このような働きかけの結果が連続して観察される様、つまり人類の歴史は横の帰り(→)の流れを示していることになる。
では横の行きの流れ(←)が進める内外のせめぎ合いによって起こる縦の行きの流れ(↑)と、横の帰りの流れ(→)は何が違うのか?
縦の行きの流れ(↑)とは個人の意志によらない影響の連鎖を個人が受け取る過程である。常に全ての環境層において個人も全人類も含めた全物質と全生物に対して事象を起こす時間の流れである横の行きの流れ(←)と区別されるのが縦の行きの流れ(↑)だ。
これに対して横の帰りの流れ(→)は、人為的な積み重ね(あるいは作り替え、書き換え)の流れである。
肉体環境(E)~物的環境(B)の外的環境に向けて個人の存続のために行動を発現することで歴史を刻み環境に対する影響を積み重ねて来たのだ。これは横の行きの流れ(←)が自然の流れであることに対して人為的な作用である点で異質なものだ。
そして、人に都合の良い人為的な影響を受けた環境層の自らに都合の良い部分(内的秩序)を認知(脳)や感知(身体)や経験(時間に伴い蓄積された個体独自の認知感知に基づく情報体系)して受け取る作用(縦の行きの流れ)と行動(縦の帰りの流れ)が噛み合うことで生存が可能となる。
以上のような作用の積み重ねによって、過去から未来へわたって続く人の営みの結果の連なりである歴史は形成される。その結果を横の帰りの流れ(→)と呼んでいる。
人が生きようとした結果が環境に刻まれた痕跡であるとも言える。
ところで地球上の自然物は、空間が質量の重いものから順に占められてゆく物理の原理によって形成される点で本論の環境層と同様の原理が働いていると言える。人も自然物の一部であるため当然の一致である。
人の営みに与える影響が下の環境層から順に規定されることを示す縦の行きの流れ(↑)を「積み上げ」という語で表すのもこういった理由による。
しかし固有の物質で形成された身体構造に従って活動できる動物である人は、一般的な自然物の働きとは異なる特性を持っている。
その特性を生かしてより良く生きようと環境要素に人為的な働きかけをして、その結果として自然現象の作用を変えたり、利用して力に変えている。
人は自然現象と同じルールを用いて(科学的な知識を用いて)人為的な縦の行きの流れを形成していると言える。
このことは特に物的環境(B)の内的秩序の影響を示す区分⇧10に見られる。このような自然に生まれる縦の行きの流れ(↑)と人為的に起こした環境層の連なりの違いを示すことが、そのまま人の営みの本質を示すことになる。
地球上で起こる事象は、物理法則で説明できる。
この事象を科学的な知識を生かして真似ることで人に都合良く利用するため、物資源に働きかけ築き上げたのが文明である。この人の営みを縦の行きの流れ(↑)という概念を軸に明らかにしようとしているのが本論である。
縦の行きの流れ(↑)は、重いものから軽いものにかけて順に空間を満たしてゆく自然科学の法則と同様の現象を示している。
ただし、縦の行きの流れ(↑)で認知される各環境層の状態は人為的に築かれた仕組みや個人の生存に関わる要素(内的秩序)のみであり、人の意識を超えた強大な横の行きの流れ(外的環境)とは区別される。
この意味で自然現象とは区別される認知上の過程を意味するのが縦の行きの流れ(↑)だ。(2021/10/15)
人工物と自然物
個人の行動に至るまでの力の流れと、その行動が及ぼす力の流れ、それらと関わらず存在する大きな力の流れがあり、その流れの上に人工的な構造物が形状を保ち存在している。
この人工的な構造物も大きな流れの上にある物質の一つであり、自然法則の制約から逃れられない環境要素の一つである。
そして人工物はその中に人が利用価値を見出す限りにおいて、自然物と区別されて機能と性質が抽出され利用されるのだ。
その意味で自然物と人工物は大きく区別されるのだ。人の意思とは関係なしに流れる時間に伴う大きな力の流れの中にある全物質から、人に関わり利用されるものは判別され意味や要素や機能が区別されるのだ。
更に言えば、自然物か人工物であるかを問わずに利用できるものから必要な要素を取り出して利用しているのだ。(2022/6/8)
横の行きの流れ(←)の中にある横の帰りの流れ(→)
これを流れと言って良いのか分からないが、人が環境に与えた影響の結果として現れる事象の、時間経過に伴う移り変わりを意味するのが横の帰りの流れ(→)だ。
この流れは本来は生物と自然環境の関わりによって成り立つ生態系の中で恒常的に見られるものだった。自然環境と生物が互いに影響を与え合っているのは自明のことだ。
しかし、人による横の帰りの流れ(→)だけは従来の生物が環境に与える影響とは強さの度合いが違う。
それほど強い影響力を持つことになったのは、組織的行動により生み出された文明による人工物の堆積した生活環境を世代を超えて引き継ぐことを可能とした人の特異な能力のおかげだ。
個人の能力のみに頼らず、集団による統合的な意思によって生活環境は生きやすいように作り上げられた。そして集団内で認識を共有する道具である言語を用いて、世代が変わっても作り上げられた環境を活かし、更に改善や更新を積み重ねることを可能とした。
このような漠然とした表現では伝わりづらいので、各環境層においてどの様に影響を積み重ね、世代を引き継いで文明を発展させてきたかの経緯を説明することを通じて横の帰りの流れを見てみたい。それを知る手掛かりが歴史という分野だ。(2021/7/21)
関連する項目
横の帰りの流れ(→)に関連のある42区分を以下に示す。
・⇨3 地球の構造が成立する過程
・⇨8 物資源の利用と消費
・⇨13 家族集団による生存活動
・⇨18 分子単位の生体維持活動
・⇨23 内臓器官による運動準備から発生に至る働き
・⇨28 生態に有益な情報の峻別と整理
・⇨33 他者との境界形成
横の帰りの流れ(→)に関連のある用語について述べたページを以下に示す。
・内的秩序
・横の行きの流れ(←)
・縦の帰りの流れ(↓)
・縦の行きの流れ(↑)
考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。
・4つの流れ理論
