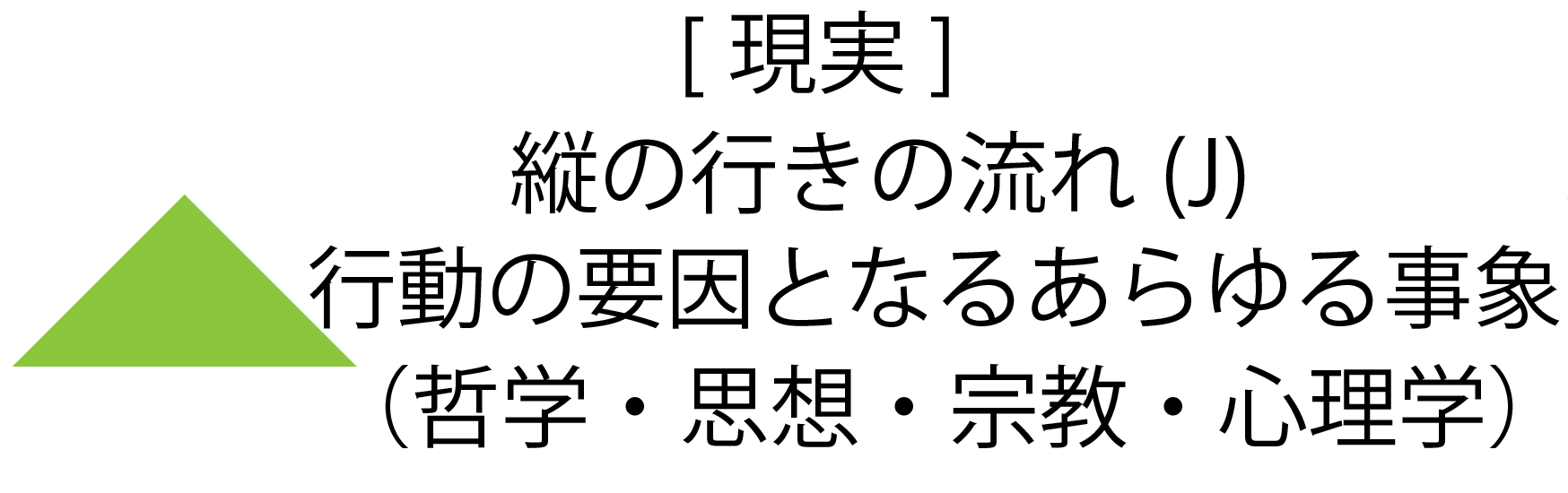
目次
- 縦の行きの流れ(↑)とは
- 縦の行きの流れ(↑)の定義
- 縦の行きの流れ(↑)の原動力
- 縦の行きの流れ(↑)を推進する力
- 環境要素の力関係の影響
- 縦の行きの流れ(↑)で抽出される境界
- 行きと帰りの概念の発想
- 行きと帰りの概念と因果
- 縦の行きの”流れ”は存在するか
- 縦の行きの流れ(↑)と物理法則
- 縦の行きの流れ(↑)の働き概要
- 縦の行きの流れ(↑)の働き詳細
- 縦の行きの流れ(↑)の例
- 縦の行きの流れ(↑)と環境の入れ子構造
- 個人と環境の関わりの深さ
- 縦の流れと人の営み
- 環境層と環境要素
- 無意識と意識の境界
- 縦の行きの流れ(↑)と脳に伝わる情報の質
- 行きの流れと身体の成長・繁殖・人口増加
- 4つの流れの連鎖の順
- 縦の行きの流れ(↑)における空間と移動可能性
- 関連する項目
縦の行きの流れ(↑)とは
無意識下の身体調整によって内的秩序と外的環境のバランス均衡が保たれる現象を示すのが縦の行きの流れ(↑)だ。
このバランスの不均衡に対して「やるぞ」「やらなきゃ」という信号が起こり始める、つまり行動(移動・行為)に繋がる流れが発動するのが縦の帰りの流れ(↓)であると考える。
こうすることで縦の行きの流れ(↑)の定義がよりはっきりする。無意識下で内外のバランスがせめぎ合っている状態であると。(2022/8/10)
横の行きの流れ(←)の一時点における環境層の状態を認知に繋げて行動に影響を与えるのが縦の行きの流れ(↑)である。
これはある一時点において個人が環境から受け取る影響のまとまりを意味する概念だ。この縦の行きの流れが行動を決める要因となり縦の帰りの流れ(行動)が生まれる。(2021/2/12)
縦の行きの流れとは。
縦の帰りの流れ(行動)が発現する瞬間までに堆積した環境層の影響を総合的に受け取ったもの。瞬間の認知という神経細胞の働きによるものに限らず、蓄積された体調や経験など行動の基盤となるあらゆるものが縦の行きの流れの構成要素となる。(2021/10/10)
縦の行きの流れ(↑)の定義
個人にとっての環境層とは、行動に与える影響の強さの度合いによって分かれて連なった環境要因の集まりだと言える。
環境層とは、物質の性質の違いに基づいて行動発現に至る要因と結果の現れ方に影響を及ぼす要素の集まりを意味する。
この行動の要因となる要素の連なりを縦の行きの流れ(↑)と呼ぶ。これは環境層の自然環境(A)から心的環境(G)で折り返して行動に至る要因の連鎖を意味する。
正しくは「流れの要因」であるが、この点において厳密な表現をすることの重要度は低いと考えてシンプルな表現とした。(2021/9/5)
縦の行きの流れ(↑)の定義について。
強制力を伴う非可逆的なエネルギーの流れ(横の行きの流れ←)によって地球の事象は支配されている。究極的に全ては一方向に進んでいるのだが、空間には様々な物質が存在し、加えられた一定のエネルギー量に対する挙動は物質により異なる。
その結果として物質ごとに異なる状態となり、その差異が流れを生み出す。
こうして生まれた複雑な流れが一定の循環性を持った澱みとして現れたものが生物の原型となる。
この横の行きの流れ(←)から派生した複雑な流れを意味するものとして定義したのが縦の行きの流れ(↑)である。(2021/4/25)
縦の行きの流れ(↑)の原動力
環境層の自然環境(A)は地球の現象の大元として定義した区分だ。
地球は重力で人を引きつけて制約を与え、人に限らず地上のすべての物質に影響を与え続けている。当然、太陽の働きはすべての地球上の物質に作用している。
人の行動として観測される生態は、継続的に与えられる太陽や地球、自然環境からの作用とエネルギー供給に同期するように発現する。そして人の行動は、生物個体として重力に逆らって直立し、歩行し、時には機械を使って空をも飛ぶ形で現れる。
太陽から与えられる大きなエネルギーが地球に存在する物質に作用して、変化と活動を促している。その結果が具体的な行動として現れるのだが、そこに至るまでには複雑な過程がありそうだ。
その過程とは大元のエネルギーが形を変えながら最終的に生物個体の生命活動によって消費される流れである。
その複雑な過程において、個人の周囲の様々な要素が作用している。これを「環境要素」と呼び、その環境要素の特性を分類すると7つに区分できる。
そして、その7つに分かれた環境要素のまとまりは個人を包む膜のように7つの層として存在する。この層は人の行動がどのような形で現出するかを決めるフィルターの役目を果たす。
大元の太陽のエネルギーが最終的にどのような人の行動を生み出すか、そこに至るまでの環境層は次の7つだ。
自然環境(A)、物的環境(B)、生物環境(C)、情報的環境(D)、肉体環境(E)、人的環境(F)、心的環境(G)。これらが人の行動発現の様態に関わるフィルターとして働く。(2020/7/23)
縦の行きの流れ(↑)を推進する力
各環境層は、それぞれ性質は異なるが質量は同質に近い要素の集まりとして構成されている。そのため構成要素同士は常にせめぎ合っており、境界は不確定である。
それに対して、環境層の間の境界は明確だ。
こうした構造上、縦の行きの流れでは環境層ごとの内外の関係が自然に上の層に連鎖することで内的秩序の範囲が段階的に狭まるようになっている。
こうした縦の行きの流れ(↑)という現象を推進する原理は何か?はとても重要な問いだ。空腹の状態が食欲を誘発して摂食行動を起こすまでの流れを例に考えられそうだ。
↑を推進する動力は←に対する→であることは確かだろう。
↑もそれに繋がる↓も単なる→の派生の流れと言える。よって←に対する→は物理的な特性で説明ができるため、物理的な実験モデルを作ることも可能かもしれない。それを通して↑を推進する原理を明らかにできるかも知れない。そうなれば夢のある話だ。(2022/8/10)
環境要素の力関係の影響
力とは何か。それは各環境層における環境要素の間の相対的優位性を意味する。
各層における力関係の固定化、安定化が進行するに伴い、各層において実現可能な内的秩序の最大値に近づく。
これはその層の要素間の力関係に基づくすみ分けの完成を意味している。そして上に重なる環境層の積み上げの土台となり、更に上の層においても最大限の調和に向けて力関係をめぐるせめぎ合いが展開される。(2020/6/25)
縦の行きの流れ(↑)で抽出される境界
縦の行きの流れ(↑)によって人は競争に駆り立てられる。
人は各環境層の綻びや歪みを認知、感知して見つけそこに向けて資力を投じる(縦の帰りの流れが発生する)からだ。それは正しく平和な力の行使も、悪しき暴力的な行使も含まれる。その流れは人が生きている限り止まらない。 (2021/3/1)
行きと帰りの概念の発想
何はともあれ自然環境(A)から上がって来たエネルギーは何らかの行動として放散される。たとえ心的環境(G)が機能しなくても、行動そのものを成立させようと望む力は止めようがないからだ。
しかし無制約に行動が成立するはずはない。
自然環境(A)で発生したエネルギーは物的環境(B)、生物的環境(C)、情報的環境(D)、肉体環境(E)、人的環境(F)、心的環境(G)と連なる多くのフィルターの影響を受け、規定された行動として発現する。
その行動が内包するエネルギーの量と方向性、つまり力の内訳がその行動によって物事を動かす要因となる。
ここまでの説明で、私たち人間の営みの全容を示す流れのうちの、言わば「行き」の過程を示したことになる。これに対する「帰り」もある。
もう少し詳しく述べると、地球を始めとする環境全ての要素が人の個体に与える「刺激」の全貌を「行き」として示したのだ。
そして個体に与えた刺激は「反応」を引き起こす。これが「帰り」であり、環境要素に対する反応は一定の力の量と方向性を持った行動として現れる。(2020/8/5)
行きと帰りの概念と因果
「行き」の流れにおいてそれぞれの環境層はフィルターのように作用して個人の行動に影響を与える要因として作用するのと同時に、各層における内的秩序と外的環境の境界を形成する基礎となる。
「行き」の流れは行動に至るまでの環境層との因果関係を示すものであり、行動に及ぼす影響を示す概念だ。これは行動が起こる過程を説明するために設定したものだ。
生命活動を最も有効に成し遂げるために、行動が発現する際にその行動に影響を与える様々な環境要素がフィルターのように作用する様子を「行き」であるとした。
そして起こした行動はその力の強さと性質により、内的秩序と外的環境の境界と環境要素に影響を与える。これが「帰り」の流れだ。
これは人の行動について因果という語で表される概念を、「行き」と「帰り」と呼ぶ大きな視点で説明する試みだ。(2020/7/14)
縦の行きの”流れ”は存在するか
縦の行きの流れ(↑)は無意識下に存在する行動要因の全容を示すもので、人の生に影響を及ぼす働きのあり方を示す概念だ。
人が生きている状態の全てを包括する概念とも言える。
縦の行きの流れ(↑)の概念は文字通り「流れ」と捉えて行動に至る要因の連鎖と考えるのが自然だろう。
これに対して↑の方向では流れと呼べるような動きは無いとする考え方もある。
この考え方では自然環境(A)を外枠として↑方向に層別に隔絶した構造があるだけとする。層間の影響は層内の要素間の働きが間接的に別の層に及ぶ形で現れるとする考え方だ。
↑において各層は構成要素の特性の違いにより異なる挙動を示す。
←と→の関係性は各層の内部で完結しているが、その関係性は上の層に向かって影響が及ぶ。
この影響が上から下へ流れることはない。↑は←に伴い発生する現象だからだ。よって、↑の影響が逆に及ぶとすれば時間の逆流に相当する現象となってしまう。
この縦の行きの「流れ」とは入れ子構造の影響の及ぶ向きを示したものと考えた方が分かりやすい。(2022/8/10)
縦の行きの流れ(↑)と物理法則
地球の長い歴史の中で同じ太陽から等しくエネルギーを受けながらも、地球上の物質は、その流動性と質量の違いによって様々に異なる機能を見せながら、現在につながる豊かな自然環境を作り出してきた。
今地球上に生きる人類もまたその流れの中にある。
時間経過に伴う物質の様態変化の要因は、物質ごとに異なる質量と流動性にある。
この原理を元に自然環境(A)~心的環境(G)に至る環境層の流れが説明できる。これが縦の行きの流れ(↑)を作るのだ。
縦の行きの流れ(↑)について。
行動の前提条件、因果の状態を示すとか、実際の力の流れを伴わないと考えたこともあるが、重要な力の流れの要因であることを改めて強調したい。それは質量と流動性の違いによって発生する『構造的要因による力の移動』だ。
高いところから低いところへ流れる水のように、重いものが軽いものを退ける現象。物理的に異質なもの同士に発生する力の流れが、縦の行きの流れ(↑)の本質である。(2021/1/28)
縦の行きの流れ(↑)の働き概要
身体をコントロールする認知や神経系の緻密な働きがどのように生まれるかについて。それは身体活動の大元である自然環境(A)の大きな流れから始まり、段階的に行動を制御するための精細な心理過程に変わってゆく仕組みによってなされる。
この段階と過程を示すのが7つの環境層と縦の行きの流れ(↑)という考え方だ。
この視点は、巨大な自然現象の全体から引き算を繰り返して、行動に至る個人の心理という小さな現象が削り出されてゆく過程を捉えている。(2022/7/5)
縦の行きの流れ(↑)は下の層から登ってくるような流れだ。↑は登りきってから縦の帰りの流れ(↓)に折り返すまで連続している。
縦の行きの流れ(↑)は行動の要因として雑多な記憶や経験からランダムに行動の要素が抽出されるのではなく、秩序立った層構造によって自動的に境界が内的秩序に向けて狭まってゆく構造を示している。(2022/8/10)
縦の行きの流れ(↑)の働き詳細
自分がまずどんな場所に居るかを考える。
人の意識は↑において各環境層ごとに内的秩序と外的環境を捉え分けた上で、↓の流れで外的環境に向けて行為を起こす。そして内的秩序と外的環境の境界の位置や状態は常に変化し、それに伴い内と外に相当する範囲も変化する。
こうした理由によって行動の質は内外の境界の有り様と内的秩序の範囲の広さに影響を受ける。
それでは実際に行動はどのように発現するかに注目してみよう。
↑において各層の内的秩序の範囲と内外の境界の状態が不安定で、内的秩序を脅かすような状態である場合に行動はその不安定さを解消する動きとして現れる。この傾向は生物としての人の生存本能に由来する不変の行動原理だ。(2022/6/8)
縦の行きの流れ(↑)の例
自然環境(A)~心的環境(G)の環境層の影響の連鎖である縦の行きの流れ(↑)は常に消化されている。この流れの順は一定であり、厳然と個人の行動を支配している。
環境層は構成する環境要素が特性ごとにすみ分けられることで安定し、その安定の上に次の層が築かれる。下の層の安定の状態は上の層に影響を与える。
積み上げの層の厚さも複雑さも頑丈さも、環境要素のすみ分けのエリアによって異なる。そのため同じ環境層でも土地や個人ごとに安定の度合いは異なる。
具体的には、生まれた土地の自然環境から始まり、体格、性別、家族、家柄、教育、国籍など、積み上がってゆくものは個人ごとに違う。
個人にとって常に環境層の最上位にある心的環境(G)の内的秩序(自己意識)は、積み上がってきた環境条件を受けとって成立している。(2020/7/3)
縦の行きの流れ(↑)と環境の入れ子構造
人の営みは環境層の影響が下から順に重なることで成立している。これが「積み上げ理論」の概要だ。その発展的概念として環境の入れ子構造がある。
これは心理学では一般的な見方だが、社会構造を一般化して平面的に捉える社会科学の見方には馴染まないものだろう。
身体というパッケージに包まれた心的環境(G)という構造。
肉体環境(E)に守られているのが心的環境(G)で、肉体環境(E)を維持して支えているのが自然環境(A)。大きな入れ子構図として想像しやすいと思う。(2020/7/7)
細胞が膜によって内部の構造を包み込み守っているように、「積み上げ理論」を構成する環境要素が集まり層を成すことで膜となり、内側の層を守っていることを説明したい。
膜に包まれていると言うことは内側と外側が隔離されていることを意味する。(2020/7/7)
個人と環境の関わりの深さ
縦の行きの流れ(↑)で行動が成立するまでの過程として、特に生物的環境(C)~肉体環境(E)を掘り下げると、各環境層の大きな影響に気付く。
それは、無意識も意識も含めた個人と環境の関わり方についてだ。
それは関わる程度や質、深さを示すものであり、その関わり方は感覚器、深層意識、空間認知、知識、体験など様々な形で「環境を受け取っている」ことを意味する。
他に適切な表現が思いつかない。つまりあらゆる影響を受けることを意味している。(2021/1/26)
縦の流れと人の営み
横の行きと帰りの二つの流れの緊張関係を逃して縦の行きの流れと縦の帰りの流れにするのが人の営みである。
「緊張関係を逃す」という表現は、人や生物を含む環境に存在する全ての物質が影響し合う中で、力の作用からは逃れ得ないという原則に基づいている。
物質は重く流動性のあるものから順に環境を形成する主導権を得て、性質の異なる物質ごとに空間にすみ分けられ、重さの異なる順に層を成す。人を始めとした生物の有り様も、地球上の物質であることから逃れ得るものではなく、そうした物理法則に順応する形で認知や感覚の仕組みも作り上げられた。
よって、縦の行きの流れ(↑)とは率直にそうした物理法則(重いものを重視する)に沿って適応した認知に至る流れを示すものと言える。その認知とは個人がその時点で環境内に存在している事実を目一杯に受け止める作用であり、それがまさに縦の行きの流れの意味する所だ。
自然現象を記述するだけなら横の行きと帰りの流れだけで可能だが、その中から人の営みを抽出する場合にはこの「縦の行きと帰りの流れ」の概念が必要になる。
これは人と環境要素が関わる中に人の営みが存在し、その関係を示すのがこの「縦の行きと帰りの流れ」であることを示している。(2021/3/1)
環境層と環境要素
環境層と環境要素、この二つの概念は縦の行きの流れを意味する代表的なものだ。
なぜなら環境層の分類や名称そのものが、個人が周囲に存在する事象をどのように認識しているかを示しているからだ。
認識できないものに人は名前を付けることはできない。つまり名称のついたものは人の認知する世界そのものを指す。
同じことが環境層の分類についても言える。それらを異なるまとまりと認識する基準は個人と環境要素の関わり方の違いによって定められる。つまり認識に基づく分類の作業そのものが環境との認知上の関わりを意味しているのだ。
さらに踏み込めばこれらの認知は事象を俯瞰的な神のような視点で眺めたり、客観的な検証に基づく科学的な捉え方でなされることは無い。あるとすれば特別な場合のみだ。基本的には自らに関わるものとそうではないものを区別して認知して、そうした認知の積み重ねが個人的な経験、知識として蓄積されているからだ
この蓄積は脳内のみではなく、体全体で受け取る経験によって脳の状態は決定している。
こうした認知や経験の蓄積は何のためになされるかと言えば生存のために必要な情報を環境から得るためである。生まれたその瞬間から母親の存在を始めとする全ての事象を受け止めながら成長する。そして生存のために何らかの事を為すのだ。(2021/10/18)
無意識と意識の境界
睡眠時に、夢の中で色々な出来事がバラバラのまま繋がっているように感じたり、空を飛んで空間を越える体験のように境界を消失する感覚について。
これは、↑の作用である行動に至るまでの過程において、内的秩序と外的環境をより正しく認識するために、その境界を安定させる必要がない状態を意味する。
覚醒時には、行動する際に正しく外的環境を捉えるための重要度の高い順に境界を確定させてゆく必要がある。
安定的に確定できるかどうかは認知にとても大きな影響を及ぼす。認知上の情報整理の過程だけで確定するのに不十分である場合は↓で行動によって外的環境の状況に働きかけ、境界を安定の状態に近づけることもできる。こうして行動の判断はなされる。(2022/6/14)
縦の行きの流れ(↑)と脳に伝わる情報の質
覚醒時の周囲状況が↑で脳に伝わる情報の質について。
↑は上の層に進むに従い内的秩序の範囲が狭まってゆく構造になっている。
ここで大事なのは範囲を狭めてゆく各区分の内容だけではなく、内外の境界の確定要因が内側(つまり自分)と外側の状況とどのように関連しているかだ。この関連の状況は常に変動しており、その状況によって境界の位置もその確かさも変わるのだ。この変動の要因は←に伴う→の動きであることも、↓による働きかけの結果であることもあり、複合的なものだ。
↓はどのように行動が現れるのかという大事な部分だがもう少し↑を掘り下げよう。(2022/6/23)
何度も繰り返しになるが、人の営みの基本的な原理である「離れたものへの働きかけ」についてまとめる。
まず縦の行きの流れにおいて、外、離れたもの、外的環境へ働きかけるための下準備である自己と外との境界を捉える仕組みがあること。その仕組みにより縦の行きの流れを通じて、個人と外との区分を明確に認識できる。(2022/6/30)
行きの流れと身体の成長・繁殖・人口増加
↑の無意識下の身体の働きについて。
興味深いのが↑の生物的環境に人の繁殖も含めている点。身体の成長や体調、体質の変化も↑に含まれるだろう。肉体的環境の↑かな。
栄養は全て運動のために消費されるのではなく、身体を作ったり維持するためにも使われるし、子供を産むのにも使われる。これは行動ではなく、無意識下の身体の働きである。(2022/8/10)
4つの流れの連鎖の順
4つの流れを重要度の高い順で並べると←→↑↓になる。
これは生まれる前から決まっている逆らいようのない秩序の順だ。
↑より→が重要度が高くなるのは、人の↑↓がとても小さく、生まれながらに存在する→(歴史)の影響がとても大きいことを意味している。この意味では生まれながらに恩恵を受ける→も←の中にあるので自然物と人工物を区別することに意味はないのかもしれない。
←→は物と自然の流れ、↑↓は人の営みの流れと言えるか。
↑も↓も内的秩序と外的環境の関係性の影響を強く受ける。
そして人生の基本的なあり方、悠久の←に乗って長い歴史を通じた→が積み重なっている所に突然命の連鎖で親から生まれるという運命性にも触れないわけには行かない。
そして、人が生きていると言うことは覚醒して行動している状態にのみ事実として言えることであり、行動の要因として取り上げた環境層という概念は思索に基づいた理論上の現象に過ぎない点も押さえたい。
本論は哲学であり、科学ではない。
冷たい事実を人間としてどのように捉えるかという探求の行為である。論文にこだわったこともあるが、何より大事なのは人に届くこと。人を忘れようとしていることへの警鐘、人の生物としての生の良さを思い出すためのきっかけだ。(2022/6/8)
文明の内側に物を取り込んでも人は人の秩序を脱することはできない。人の秩序とは内面に築かれるものであり、内面とは縦の行きの流れにあたるものだ。
「人は人の秩序を脱することはできない」ことの証明として4つの流れ理論が役立てば少しは価値を生み出せたことになるのか。(2022/6/12)
まとめ
縦の行きの流れ(↑)における空間と移動可能性
※一部「環境層」のページ内容と重複する箇所があります。
行きの流れは2つある。その一つ、横の行きの流れは時間の流れだ。もう一つの縦の行きの流れは、横の行きの流れから派生する物質の性質と質量の差に基づく流れだ。
縦の行きの流れは物理現象の連なりとして理解しやすいが、時間の流れとは何か?
それは縦の行きの流れから派生した帰りの流れの影響も含めた結果が、時間の経過に伴い堆積してゆく過程のことだ。
縦の帰りの流れとは、単位時間に起こした行動により環境要素に与える影響の総量を意味する。そして横の帰りの流れは、人の行動による影響(縦の帰りの流れ)とそれ以外の全ての自然現象の時間に伴う変化圧(横の行きの流れ)の和である。
この縦の行きの流れ、異なる環境層をまたぐ流れはどのように進むのかを示す手がかりが秩序についての考え方だ。この視点無くして実相をつかむことは不可能であり、モデルの実用可能性の核とも言える。
地球上には重力や太陽光の影響を受ける大きなエネルギーの流れが存在し、高いところから低いところへ、重く強いものが先に動いて軽くて弱いものが後に動くという大雑把なイメージは間違ってはいない。
しかし現実の地球上にある様々な地形と変動を続ける気候の多様性、生命活動の複雑さによって成り立つ生態系の豊かさを説明するには不十分だ。
そこで、まとまりや集団やシステム、系などの「異なる物質が混在する空間に起きる現象」に注目することになる。
これと生命活動や人工的なシステムはどのように関係するのか。
まず、各環境層はそれぞれ質量や性質が似通ったもので構成されている。これを環境層の構成要素(環境要素)と呼ぶ。
環境要素の集まりは限られた質量と性質の範囲内で多様性を保ちながら同一の環境層内で影響を及ぼし合っている。その過程で同質の構成要素が結びつきまとまりを作ったり、異質であっても相互に関わりのある循環系を作ったりする。
この循環系は生命活動に限らない、気象現象が良い例だ。
このように環境層内において構成要素は多様な状態で存在しているが、異なる環境層同士はどのような関係を持つか?
環境層の違いは主に構成要素の物的な特性の違いで説明できる。それが質量や挙動の違いとして現れ、異なる層として観測できるのだ。
その層の間の関わりについて把握するための重要な概念が「空間と移動可能性」だ。
下の層を構成する物質だけで空間が全て占められることはなく、上には余った空間ができる。そこを占めるのが次の層を構成する要素であり、余った空間の容量の範囲内で自由に流動できる。
上にあたる層は下の層によって有り様(活動)の範囲を規定される。空間があり、その中を自由に移動できる特性(質量)を持つ物質だけが上の層に存在できるとも言える。
各層内における流動性、移動可能性には物的特性に基づく限界があるため、限られた時間において下の層は上の層に対して固定的条件と言えるほどの制限を設ける。
地形とそこに生息する生物が異なる時間スケールの中で存在していることを考えると分かりやすいだろう。
この「空間と移動可能性」の程度や性質は環境層ごとに異なる。
層内においては異なる性質の物、異なる状態の物同士が隣り合って存在し関わりあうことでまとまりを作ったり、異なるもの同士が循環的な系を作ったり、移動可能性の範囲内で自由に動きぶつかり合う過程を経て、ある程度の安定的な位置取りを得る。
それは、下層によって移動可能性の制限を受けた上で、残された空間内で自由に振る舞い得られた多様性と言える。地域により異なる自然環境と生態系の関係が分かりやすい例だ。
この互いに接する上下層の関係性を決める仕組みは全ての環境層で共通している。
そのため、上の層に行くにつれて空間と移動可能性は狭まり、軽く早く小さく細かい系が形成されてゆく。こうして神経細胞の挙動により発生する認知の領域にまで至る。
以上のような大地から精神に至る普遍的な現象を捉えたのが環境層という概念だ。
余談だが、この「移動可能性と認知の範囲」は人の文明の発展により大きく広がったように見えるが、見方によってはどちらも人工的に細かく分解されることに伴い、限りなく狭まっているとも言える。
生まれたばかりの子供は事象を認知しない限りにおいて移動可能性は無限大と言えるが、認知されればその範囲に移動可能性は限定されてしまう。このような逆説的な理由で人は不自由になり続けている。
一方で、文明の成熟がもたらす不自由さによって私たちは守られていることも忘れてはいけない。
縦の行きの流れにおいて、各環境層の構成要素は形成されたまとまりや系の構造に従い事象を起こす。限られた空間の中で同質の物はより大きな集合を作ったり、異質な物同士は別れたり反発したり衝突し合いながら関連することでひとまとまりの系を構成する。
そしてその系で消費されるエネルギーの余剰、系の外側に発せられるエネルギーは空間と移動可能性の範囲内で自由に振る舞い、時に他の物質や系と接触する。各環境層の構成要素は常にこうした衝突と融合と組織化を繰り返す過程にある。最終的にエネルギーの流れの余剰は空間(上の環境層)へ向かう。
その大きな流れの中にある人も例外ではなく、各環境層において個人の内的秩序を形成しながらエネルギーを消費する形態が行動として現れる。
全ての環境層において横の行きの流れは存在して、内的秩序に対する侵食圧は常に存在する。
生命を脅かすその圧に対して、個人が関わる事象の体系(内的秩序)のエネルギーの出口は、縦の行きの流れの到達点から派生する縦の帰りの流れ(行動)にしか存在しない。縦の行きの流れから認知、感覚として捉えた外的環境に対し「移動可能性と認知の範囲」内で行動によって働きかけるのだ。これが帰りの流れとなる。
帰りの流れは内的秩序の系を働かせて外的環境にある他の系に接触したり接近する動きを生み出し、各環境層の状態を変える働きを持つ。
物質同士は常にそうした緊張関係の中に存在するが、人の行動は「生物個体が環境刺激に反応する」という意味づけで語ることができる。
この縦の行きの流れから派生する帰りの流れも含めた総合的な影響の結果が、各環境層の変化として観測できる。これが時間の流れに伴う全環境層における変化の様相であり、本論で横の行きの流れと呼ぶものだ。
縦の帰りの流れは人の行動に向かう事象として現れる。これは生物共通の特性である環境条件に対する反射の様子だ。そしてその結果の時系に沿った連なりが横の帰りの流れとなる。
各環境層ごとに構成要素の性質が違うため、まとまり方、系の様相、システムの性質は異なる。しかし、それらのまとまりは環境層ごとに独立して存在するわけではなく、系ごとに縦に連なる流れを持っている。人について言えば、土地・国・性別・社会などに根付いた認知基盤を持っているということだ。個人の持つ文化性とも言える。
「空間と移動可能性と認知の範囲」という縦の行きの流れを理解するための大事な点が分かったが、複雑な人間社会を理解する決定打にはならない。
鍵は帰りの流れだ。どういった形で発現するだろう。行動は個人単位で起こるが、その行動は縦の行きの流れによって既に「空間と移動可能性と認知の範囲」の制限を受けており、一人の行動であっても集団的、システム的な特性を帯びたものとなる。こうした個人の行動が噛み合うことで大きな集団とシステムを機能させる力となる。
その大きな力の起点となる個人の行動を複数人にわたり同期させて大きな力にするためには認知の働きが必要になる。
では、各環境層におけるまとまりや系がどのような縦の行きの流れを作っているかを見てみよう。縦の行きの流れにおける各環境層は行動を決める条件のフィルターのようなものだ。
行きの流れも帰りの流れも各環境層の影響を強く受けるが、縦の行きの流れの本質はその一時点における認知上の前提条件に過ぎず、実際に物事が動くのが帰りの流れであると言える。
系が縦の行きの流れに基づいて機能して(内的秩序の働き)、行動によって他の系(外的環境)に影響を与える過程が帰りの流れとなる。
縦の帰りの流れは環境層に対する働きかけである。
つまり各環境層における内外の集合間、システム間のせめぎ合いを調整し、補正する志向を持つ流れだ。状況によって強いせめぎ合いの起きている環境層は異なる。それは、縦の行きの流れを推進する内的秩序の働きを妨げる歪みである。その歪みを縦の行きの流れにおける認知、感覚で捉え、反応の行動によって歪みの強い環境層に向けて矯正、補正を志向する力を及ぼす。
一連の環境層をまたぐエネルギーの流れの中で、内的秩序の系がスムーズに働き連動が上手くいっている箇所とそうではない箇所があり、そのバランスが認知と行動に影響するのだ。
但し、これが原則であることが分かった所で人の行動がどこへ向かうか理解できる訳ではない。地震のメカニズムが解明されても予測が困難であるように、全体のバランスを測るための情報が十分には手に入らないからだ。(2021/4/24)
関連する項目
縦の行きの流れ(↑)に関連のある42区分を以下に示す。
・⇧5 生物の生息環境の成立過程
・⇧10 生息環境と生物や食料の関係
・⇧15 個人の誕生と発達の背景
・⇧20 身体形成の設計図(遺伝子)
・⇧25 身体と脳機能の関係
・⇧30 固有の自己認識と他者との協力
・⇧35 無意識
縦の行きの流れ(↑)に関連のある用語について述べたページを以下に示す。
・環境層
・縦の帰りの流れ(↓)
・横の行きの流れ(←)
・横の帰りの流れ(→)
考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。
・4つの流れ理論
