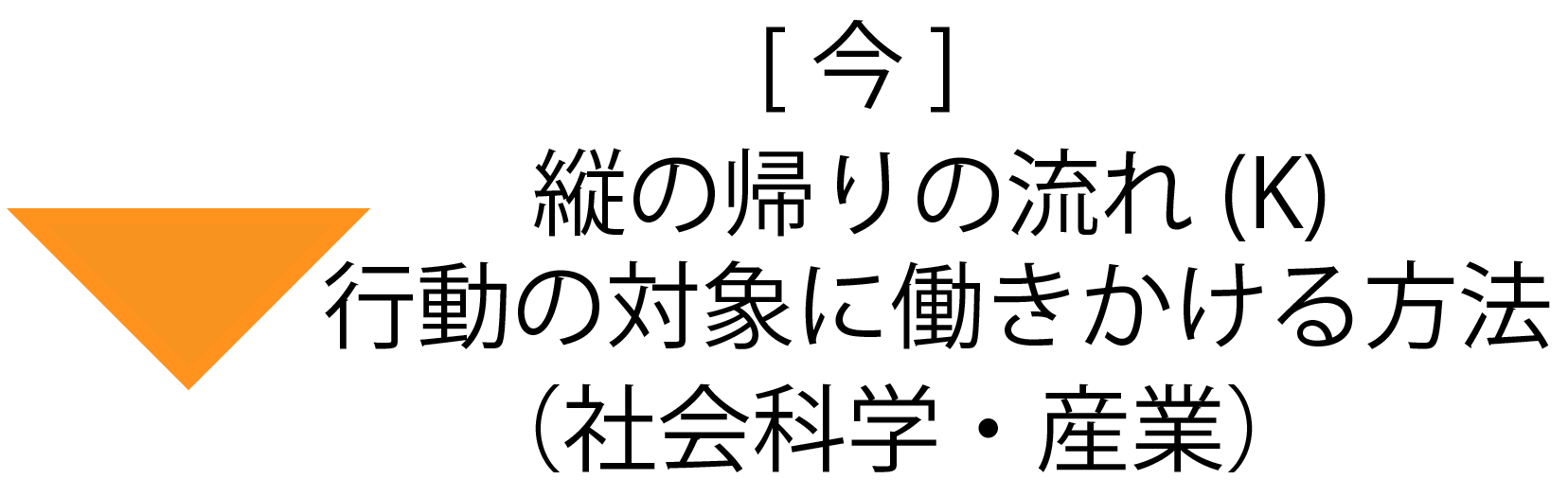
目次
- 縦の帰りの流れ(↓)の方向性
- 4つの流れの方向性と行動の現れ方の共通点
- 帰りの流れの目的〜内的秩序に取り込むこと
- 離れたものへの働きかけの過程
- 縦の帰りの流れ(↓)の発現過程
- 行動の2大要素 移動と行為について
- 縦の帰りの流れ(↓)の全容
- 「行きと帰り」の概念
- 行きの流れと私たちの生
- 行動の反射の性質と環境層
- 人という生物
- 自然現象と人の生の関わり
- 環境に対する組織的な反射
- 縦の帰りの流れ(↓)の余剰
- 縦の帰りの流れ(↓)と文化のあり方
- 人の生の本体について
- 行動について
- 行動の手札としての縦の行きの流れ(↑)
- 行動による外的環境への接触
- 行動の現れ方
- 関連する項目
縦の帰りの流れ(↓)の方向性
人の行動はただ無秩序に外的環境に対して働きかけを行うのではなく、各環境層の内的秩序を正したり維持する方向で発現する。
各環境層における自律的な身体の働きに基づく内外のせめぎ合いを、縦の行きの流れ(↑)で敏感に受けとり、その時々によって異なる境界へ働きかけるのだ。
横の帰りの流れ(→)による各層の内的秩序から外的環境に及ぼす影響によって、縦の帰りの流れ(↓)は推進される。行きの流れにおける縦と横の関係と同様に、帰りの流れにおいても縦と横は合成された一つの現象として現れる。
この意味で4つの流れを2つの大きな流れに分類する場合は、行きと帰りで分けることが適切である。縦と横は自然現象の全体から人に関する現象を意図的に抽出するために分けた区分に過ぎないからだ。(2021/2/1)
4つの流れの方向性と行動の現れ方の共通点
私たちにとって身近であり、最も巨大な自然物である地球の影響は、地面に接する足から身体の様々な器官を経て脳に至り、それに対する反応である行動によって力を地面に伝え返す形で現れる。
驚くことに、地面から重力に反して上に向かって働く空間的に↑と↓の方向性を持った身体運動の様態と、本論における縦の行きと帰りで説明される現象が一致していることが分かる。
これは偶然ではなく、本論が物理法則によって検証可能な現象を示しているからであろう。
上に物を運ぶためにはエネルギーや労力が必要だ。そうしたエネルギーによって直立して生存することが縦の行きの流れ(↑)。一定の高さへ到達した後にエネルギーの流れは異なる経路を辿る。それが縦の帰りの流れ(↓)である行動だ。(2022/6/14)
帰りの流れの目的〜内的秩序に取り込むこと
縦の帰りの流れ(↓)とそれを推進する横の帰りの流れ(→)は全て「外的環境に働きかけて内的秩序に取り込む」目的で発生する。この目的は幅広い意味を持つ。
例えば身体を思い通りに制御して目標の場所に移動して、その場所の一定の面積を身体の容量(縦横で50cm程)で占めることも「外的環境に働きかけて内的秩序に取り込む」ことを意味する。他には生物を食して体内に入れること、他者と関わること、一緒にいることも当てはまる。
「外的環境に働きかけて内的秩序に取り込む」ことは生物に限らず物質の持つ根源的な性質であるから、様々な事象がどのように当てはまるかの検証の余地が大いにある。(2022/6/16)
離れたものへの働きかけの過程
「離れたものへの働きかけの過程」という語は深遠だと思う。
これは人の営みの全てを意味するような概念であり、理論を通じて伝えたい事実の一つだ。
本論で記述しようと試みる事象は人の営みであり、個人に関わる経済や政治、文化といった堅苦しい内容だ。しかし、その探究の中で人を相手にした愛情という要素を無視していたように思う。
人の営みの大事な要素なのに。
離れたものへの働きかけの対象は、時に魅力的な異性であり、生きるための食料であろう。人の生の2大要素だ。(2022/8/10)
縦の帰りの流れ(↓)の発現過程
縦の帰りの流れ(↓)は環境層を上から順に辿る形で現れる。
これは行動(行動に至る意識の発生も含む)による働きかけの優先順位と言い換えることもできる。
行動につながる意識の発生から近いもの程働きかけ易く、内的秩序への取り込みがし易い。
よって縦の帰りの流れ(↓)は、まず最も近い環境層である心的環境(G)に働きかけて、それによって望ましい秩序形成ができない場合に対象となる目標が下の環境層へ及んでゆく。これはトライアンドエラーの繰り返しで、何度も縦の行きの流れ(↑)のフィードバックを得ながら行動の詳細が確定してゆく。(2022/6/23)
行動の2大要素 移動と行為について
縦の帰りの流れ(↓)の現れ方について述べる。行動の2大要素とも言える移動と行為について。
離れた対象に働きかける行動は何らかの目的をもって発生する。
その目的は概ね、内外の境界の不確かさの解消である。そして望ましい行動の発現には神経の働きを統合した正確な身体制御が必要となる。これは離れた対象に働きかけた結果として望ましい成果を得る可能性を高めるためだ。
そのため、行動は各層の境界の状態をできる限り正確に把握し、不確かな部分を解消しながら複合的な効果を期待するものとして現れる。
例えば(自然環境において)獲物に近づく・(生物を)捕らえる・(肉体に取り込み)食す・(分子情報から必要な働きを取り出し)消化するといった感じだ。単純な説明だが、一つの行動で別々の環境層に働きかける一連の流れがあることが分かる。
この例は最も原始的なものだが、現代においては行動に道具や言語が伴い重要な働きをする。(2022/6/23)
縦の帰りの流れ(↓)の全容
縦の帰りの流れ(↓)は行動が発生する過程を段階的に示したものだ。
その前段階である縦の行きの流れ(↑)における自然環境(A)は、気候などの基礎的な環境条件の安定によって身体の恒常性を維持する上で最重要の条件だ。
それに続く環境層(B)~(G)においても段階的に内的秩序の範囲は狭まるが、その内的秩序の恒常性が自律神経の働きによって維持されることで人という生物の個体は成り立っている。
このような縦の行きの流れ(↑)から派生する縦の帰りの流れ(↓)で意識が発生する場合においても、最も重視される目的は身体の生命活動を維持し続けることだ。横の行きの流れ(←)に対する横の帰りの流れ(→)の定義が「内的秩序を維持する系」である点とも矛盾しない。
この横の帰りの流れ(→)は「行動による内から外への働きかけ」と、身体の自律的な働きによって起こる「外からの働きかけに対して内の系が維持される現象」の2つの意味を持つ概念だ。
しかし行動によって地球の気象条件に直接働きかけることはできない。できるのは身体を移動させて行為をすることで自律的な内的秩序の働きを助けることのみだが、2つの働きは緻密に噛み合って人の生を構成している。
上述の自律的な働きについて説明する。
横の帰りの流れ(→)は環境下で身体を維持し続ける働き、つまり横の行きの流れ(←)の時間経過に身体が耐え続けている状態を意味する。
この「時間経過に耐えて身体の状態を維持する」現象は、存在する様々な物質に対しエネルギーが加えられた場合の、各物質ごとの反応と状態変化の差異によって引き起こされる流動的な状況下で現れる。
その結果として時間経過に伴う変化の大きな物質群と、小さな変化で済む物質群、一定のパターンを持った反応と状態変化を繰り返すようになる物質群が観測される。この3つ目が生物だ。人も含まれる。
この3つ目の物質群が時間経過に耐えて状態を維持し続けることは端的に生存を意味する。行動はその自律的な働きを後押しする方向性で発現する。
こうして発生した横の行きの流れ(←)は内的秩序と外的環境の関係を変えながら縦の帰り(↓)の流れを生み出す。行動の詳細な有り様は横の帰りの流れ(→)として観測される。↓は→に推進されて起こる現象なのだ。
まとめると→も、↓も、環境下における生存の維持を指向するということだ。人が生存を続けることは、身体器官の循環系が働き続けることを意味し、それが停止して変化のない状態が死だ。
その縦の帰りの流れ(↓)が積み重なることで、新たな行きの流れを作る。行きの流れが複雑になる程度に比例して、縦の帰りの流れ(↓)も複雑になる。
現代社会の複雑な構造はその結果と言える。縦の行きの流れ(↑)の本質である認知過程(行動に至る前提となる要因の統合的な受容)はその複雑さの結果を受け取っているに過ぎない。(2021/1/25)
「行きと帰り」の概念
「縦」の流れという概念について。
これは積み上がった環境層という考え方から理解しやすいが「行き」の流れとはどういうことか。
それは「帰り」も想定した概念である。環境から与えられる刺激に対し反応して環境に影響を与え返す関係を「行きと帰り」の流れと表記したのだ。この縦の帰りの流れも厳密には流れそのものではなく流れの要因の連続的な繋がりを示す概念である。(2021/9/5)
行きの流れと私たちの生
人にとって「行きの流れ」は逆らえない影響の連鎖だ。
よって、私たちの営みの本質と呼べるのは「帰りの流れ」である。環境に対する反射作用である行動の有り様は必死で生々しい。だがそれが私たちそのものなのだ。
私たちはたとえ生きたくなくても生かされる。「行き」の流れである自然環境から湧き上がるエネルギーの強さによって。
その力を得て環境に抗いつづけるのが私たちの人生だ。知らないうちに湧き上がってくる力なんて知ったことではない。未来を変えるのはその力の使い道次第だということか。
湧き上がってくる逆らいようのない環境の力の流れに翻弄されながら、逆らわずに何とかいなして、時には少し掘り崩し、作り変えながら生きてゆく。その本質に今人類は立ち戻っているのだ。(2020/8/5)
行動の反射の性質と環境層
自然環境(A)から発生したエネルギーの流れは個人の身体に刺激を与え、その身体は反射して環境にエネルギーを与え返す。
これは体内で代謝などの循環に費やされるのではなく、行動として消費されるエネルギーの流れを示している。
自然環境(A)から心的環境(G)に至るまで満遍なく個人に伝わる刺激、本論における「行きの流れ」は個人の身体内のエネルギー循環系の全てに影響を与える。そしてその刺激に対する反射、言わば「帰り」のエネルギーの流れは行動によって放散される形で現れる。
行動は固有のエネルギーの量と方向性を有しており、その内容を規定するのは縦の行きの流れ(↑)、個人と周囲環境の力関係だ。
行動が発生した後のエネルギーの流れについて述べる。行動は環境に影響を与える。そもそも生物は環境から資源を体内に取り込むことで生存を可能とする存在であり、絶え間なく環境に働きかけるものである。
その行動の影響は、それが発生するまでの自然環境(A)~心的環境(G)にかけて影響を受ける流れ(縦の行きの流れ)に反するように環境層を逆の順を辿って及んで行く。
まさに反射と呼ぶにふさわしい現象が起こる。
だが生物のエネルギー循環の観点から見ればこの現象は、自然環境から得た生命分子によって構成される細胞が一定の代謝反応を繰り返すのに必要な資源を、その循環構造の外側の環境から取り入れることに他ならない。
人の営みも全てこの現象の延長として環境に影響を与えていると捉えて差し支えないだろう。(2020/8/5)
人という生物
自然界の大きな流れの一部、澱みの一つが人という生物であり、遺伝子の働きにより、どの人も概ね似たような挙動をする。
そして個の人は、その澱みの中心である意思の只中に存在している。
哲学的な表現に思えるが、自然科学的に心理現象の存在を規定している。
この自然界における澱みという性質は、全生物にとって共通のものだ。
まずその澱みが周囲の物質循環系と隔離された独自の系であること。ただし共通の遺伝子を持つ系(同生物種の個体)同士は、外環境を隔てた状態でも挙動を同期させ、擬似的な循環系を作れる。
これが繁殖行動を含めた集団的な行動として現れる。
「外環境から隔離された循環系」という生物一般の定義に当てはまる私たち人類。
個人が自己を認知する主体は、その個人の挙動の中心である脳の働きの中にある。
その個人の挙動、営みについて分析するためには横の行きの流れ(←)とは分けて考えるべきだろう。厳密には個人も横の行きの流れ(←)に含まれるが独自の生物としての循環系を維持しているので区分が可能だ。
そして、人の営みは個人独自の行動体系だけではなく、高い精度で挙動を同期した集団の秩序を形成している。別個の生物の挙動を、大規模な集団でかなりの高い精度で同期させている存在として人類がある。そして同期させるツールとして言語や多種多様な人工物、文字情報を用いている。
以上のように、横の行きの流れから隔離された澱みの一つとして人類の挙動は縦の帰りの流れ(↓)を生み出している。
当然に世界には様々な生物が存在し、それらも横の行きの流れ(←)において複雑なエネルギーの流れの澱みの一部を形成している。しかし人にとっては、それらの他生物も外環境の一部であり横の行きの流れ(←)に含まれるものだ。
縦の流れとは全現象を包含する横の行きの流れから人の営みだけを抽出した概念なのだ。他生物も含めた全ての環境要素は一まとめに横の行きの流れ(←)に含まれて、その流れの派生として人の行動につながる縦の流れが生まれる。このように人を中心とした概念だ。認知を経て発現する人の行動を特別なものとして、自然現象から意図的に抽出したものと考えると良いかも知れない。(2021/4/25)
自然現象と人の生の関わり
縦の帰りの流れ(↓)は二つの側面を持っている。
反射の力を伝える過程を示す側面と、その力が環境要素にぶつかり様相を変えさせる側面、つまり横の帰りの流れ(→)との関わりだ。
この意味で人の意思による行動を意味する縦の帰りの流れ(↓)は、縦の行きの流れ(↑)と異なる。縦の行きの流れ(↑)は、横の帰りの流れ(→)と横の行きの流れ(←)の関わりによって推進される現象だ。
この関わりにおける横の帰りの流れ(→)は具体的には、細胞の代謝作用や体内の生体維持の働きを意味する。睡眠時に活発になる生体活動もこの縦の行きの流れ(↑)に含まれる。
各層には、それぞれに内的秩序(生物種、集団、生態系、社会など)が存在するが、縦の行きの流れ(↑)はこの内的秩序の働きによって成り立っていると考える。
実際には内的秩序と外的環境のぶつかり合いや重なり合い混ざり合いが常態の混沌によって成立している。この様に内と外の境界を明確にはできないので、内外の関係に基づく縦の行きの流れ(↑)は理論上の区分によって定義した概念に過ぎないのだが重要である。
行きと帰りの流れが混ざり合っている状態は、言い換えれば生物と非生物の混じり合い、或いは融合である。
行きと帰りの融合的な縦の流れのあり方は地球の自然界の有り様を示すものである。
同時に、本論では人の意思による行動とは区別される身体と環境の関わり方そのもの、個人の身体がどの様な状態で周囲環境と関わっているかという、行動に至る前提条件を示すものである。
言い換えれば発生した現象そのものを指すのではなく、その発現に至る瞬間の一時点における環境に存在する物質の状態を示すものであると言える。
自然界に存在する物質は一定の秩序を持った組織や流れやシステムを形成し、その外の流れやシステムと衝突したり混ざり合ったり、避けたり関わりながら存在する。
これらの現象は豊かな自然の景観を形作っている。そのなかで特徴的な挙動を見せるのが生物であるが、これも生物個体のシステムと周囲環境の区別が明確な点を除けば、自然界の基礎的な流れやシステム同士の衝突や混ざり合いや回避と同一の現象内に捉えられる。
つまり一般的な生物の活動もまた横の行きの流れ(←)に含まれるのだ。
では縦の行きと帰りの流れは何を意味するのか?
この概念を取り上げるのは、自然の一部として存在していた原始時代に比べて、人が環境に対する影響力を増した問題点を明らかにするためだ。そのために人の行動を自然界の大きな循環から抽出して捉える必要があるからだ。これにより取り出した人の営みを自然現象全体の中に改めて位置付けることを通してその意味を問い直したいのだ。(2021/7/21)
環境に対する組織的な反射
縦の帰りの流れ(↓)は人の行動が各環境層に影響を与える過程を示す。
一般的に動物の活動は環境刺激に対する反射(反応)として現れ、その活動は環境に一定の影響を与える。しかし縦の帰りの流れ(↓)は一般の生物ではなく人による影響だけに注目した概念である。
元来この力は縦の行きの流れ(↑)の強さに比べて小さく環境を大きく変えたり破壊するほどでは無かった。しかし人の行動による影響力は他の生物とは違い、「環境に対する組織的な反射」とも言えるような性質を持っていた。
これは個人が環境に与える影響が他の生物と同程度であっても、組織的な性質を持った行動により環境に働きかけることを通じてより大きな変化をもたらしていることを意味する。
これは同時期、同場所による直接的な組織行動に限らず間接的な影響も含む。間接的な影響には人特有の情報処理能力が関わる。
この「環境に対する組織的な反射」は、反射というだけあって環境層の縦の行きの流れ(↑)から心的環境(G)で折り返すように逆の順に影響が及んでゆく。(2021/7/21)
縦の帰りの流れ(↓)の余剰
横の行きの流れ(←)によって引き起こされる、もう一つの重要な流れが縦の帰りの流れ(↓)だ。
これは生物が身体構造によって周囲環境と隔てられた独自の循環系を維持することにより、生命活動を続けるという基礎的な特性によって起こる現象だ。
本論では人の営みに着目しているので、ここでは人の生態と行動に関わる流れを示す。
行動は横の行きの流れ(←)の強い力を受け、なおかつ縦の行きの流れ(↑)を受けながら、それらに反する(あるいはその流れとは異なる固有の)現象として現れる。この行動には縦横の行きの流れの余剰エネルギーが用いられる。
その余剰の量は文明の進歩により大きくなった。
その用いられ方も変わり続けているが、縦の帰りの流れは各環境層に何らかの影響と変化を与える。こうして人が受け取り利用した余剰エネルギーは仕事を終える。人に利用されずに放散する分も多くあると思われる。(2021/1/28)
縦の帰りの流れ(↓)と文化のあり方
手の延長としての道具を含めた内的秩序を示すのが物的環境(B)である。
↑が折り返して↓になって行動が発現する際に手足の先に付属した道具として利用する行為は文化の定義にも通じる。
その行動が現れる時に利用する物、道具そのものだけではなく、使い方と作り方から構造まで含めた行動の現れ方の全容、物と人が組み合わさった営みの現れが縦の帰りの流れ(↓)である。
この観点に基づいて、物や道具は手足の延長として捉え得ると考える。このように物と人との関係を捉えればシンプルに記述できる。(2022/6/19)
人の生の本体について
「人の生が行動により維持されている」と言う記述は誤解を生むだろう。
人の生は内臓の働きにより維持されているからだ。その働きは横の帰りの流れ(→)の一つであり、それに連なる現象である縦の行きの流れ(↑)の元となる。
縦の帰りの流れ(行動)は縦の行きの流れ(無意識の自律的な働き)の派生である。
この解釈は一般的なものであり一見の目新しさはないが、環境層に対する反射という構図で説明する点において異なる見方と言える。
無意識下に人の生は存在し、それは各環境層ごとに大きな流れによって侵食の圧を受け続けている。(2022/8/10)
行動について
個人にとって各環境層は常に時間に伴う変化の流れにさらされている。
その変化の流れに人はただ翻弄されるだけであろうか?
意思を持った生物である人は環境要素と関わり合いながら生存を続けている。これは人が環境要素に働きかけて一定の変化をもたらしていることを意味する。その働きかけを長い歴史を通して積み重ねた結果、現代の文明は成立している。
この働きかけは行動によってのみなし得ることから、「行動」という概念に注目することになる。(2021/10/13)
行動の手札としての縦の行きの流れ(↑)
一定時間内にできる行動は限られている。
万物に等しく横の行きの流れ(←)は存在するからだ。よって限られた時間内で限られた物的資源、情報を用いて行動をなすことになる。ことを成すには優先順位の決定と行動に至るまでの時間制限がポイントだ。
生態系では常に生物個体間の力の差異に起因する融合・隔離・排除の選り分けが起こっている。
特定の生物個体にとって有益な資源があれば、その個体を中心とした生物同士の融合・隔離・排除はさらに進む。
これを人に当てはめると、貨幣制度と物資源に支えられる産業と経済活動の成果になる。
融合・隔離・排除は、各環境層の要素間におけるせめぎ合いの調整の結果として起こる主要な秩序形成の作用だ。これは内的秩序と外的環境が形成される過程を説明する際にも大事な着眼点となる。
分かり易く「個人が意見の合わない他人に対峙した場合に取る手段」と言い換えることもできる。
和解して意見を一つにするか、距離を取るか、相手を排除してしまうか。
3つ目は極端に思えるが実際に起こる場合もある。限られた時間と資源の中で取り得る手段は限られる。誰もが常にそのような選択に迫られながら答えを出してきた。
この一定の時間内の手札とも呼べるものが縦の行きの流れ(↑)の各環境層だ。
そして縦の帰りの流れ(↓)で行動を発現させて環境層に働きかける。これにより手札が変わる。また一定の時間内で行動の内容を決める。この繰り返しだ。(2021/1/26)
行動による外的環境への接触
内的秩序の余剰エネルギーは外的環境の「空間の自由度と移動可能性」の範囲内で自由に振る舞い、時に異なる秩序体と接触する。この内的秩序の余剰によって発生する現象が行動である。
全ての環境層ごとに横の行きの流れ(外的環境の影響力)は存在し内的秩序とせめぎ合っている。外的環境に存在する異なる秩序とのぶつかり合いもある。
しかし余剰のエネルギーは常に行動として発現する。縦の行きの流れ(↑)を通って認知、感覚として捉えた環境条件に対し、「移動可能性」と「認知の範囲」内で行動により働きかける。これが縦の帰りの流れ(↓)だ。
これは内的秩序を運用して他の系に接触したり接近する動きや流れを意味し、各環境層の状態を変える働きを持つ。(2021/4/23)
行動の現れ方
鍵は帰りの流れだ。どのような形で発現するだろう。
行動は個人単位で起こるが、その行動は行きの流れによって既に「空間と移動可能性と認知範囲」の制限を受けており、一つの行動であってもシステムや集団の一部としての特性を帯びたものとなる。
これが大きな集まりを動かす力、他のまとまりに影響を及ぼす力となる。
この大きな力の起点となるのが個人の行動であることは変わらない。多くの個人の行動を同期させて大きな力にするために認知の働きがあるのだ。
では、各環境層における内的秩序、系のバリエーションはどのようなものか見よう。そして、それらがどのような縦の行きの流れ(↑)を作っているかを見よう。そしてそれらが行動に与える影響を見てみよう。
各環境層は行動に至るまでのエネルギーの流れのフィルターのようなものだ。それらのフィルターとしての性質は如何様なものか?そしてその性質はどのように変わっているか?
行きの流れも帰りの流れも各環境層の影響を強く受ける。しかし縦の行きの流れ(↑)は行動に至るまでの一時点における認知・感覚上の過程に過ぎず、縦の帰りの流れ(↓)が行動の本流と言える。
内的秩序と外的環境は入れ子構造になっている。
概要図で示される通り、内的秩序はその上の層における外的環境として機能する。この重なりによって縦の行きの流れ(↑)が生まれる。
縦の行きの流れ(↑)の中で内的秩序が動き、それが上の層における外的環境となり、その層における内的秩序に影響を与える。
この構造の繰り返しであるが、行動の前提となる横の行きの流れ(=外的環境の影響)は常に帰りの流れ(=内的秩序の影響)を受けて変わり続けている。
帰りの流れは内外のせめぎ合いを生み出す力であり、そのせめぎ合いの激しさが最も高まる環境層は状況によって異なる。
その歪みを内包した行きの流れが発生し、帰りの流れによってその歪みの原因となる内外関係の圧力を解消する働きかけをする。各環境層を通して安定でないところを補正する力が働くようだ。
環境層をまたぐ一連のエネルギーの流れのうち、系がスムーズに働き連動がうまくいっている箇所とそうではない箇所があり、そのバランスが認知と行動に影響するのだろう。
地震の発生メカニズムが解明されても予測が困難であるのと同様に、その時々の行動(帰りの流れ)がどこへ向かうかは全体の力関係の複雑なバランスの結果として現れるものであり、予測は困難だ。(2021/4/23)
身体の刺激や感覚に対する反応は生存可能性を高める合理性と、安定層と不安定層のバランスの調和の2つの要因で現れる気がする。
周囲環境は常に変わるので目まぐるしく、身体はそのバランスをとる行動を発現させているのだろう。
そして↑と↓の対応関係も密接であり↑で受け取る内的秩序の状態を前提としてそのシステムを発動させ生かすように行動が発現する。
道具であれ他者であれ身体であれ、そのものが持つ性質が行動の現れ方を決めるのは当然だが、それを↑で把握した上で行動を発現しなければそのシステムや特性の恩恵は思い通りに得られない。(2022/6/19)
関連する項目
縦の帰りの流れ(↓)に関連のある42区分を以下に示す。
・⇩36 意識
・⇩37 正常な行動発現
・⇩38 行動・生活様式の背景となる価値観
・⇩39 社会活動に伴う周囲情報との接触・処理方法
・⇩40 他者・他集団との接触により生起する不確定かつ反復性のない変化の軌跡
・⇩41 人と他生物・人同士の生存競争力を補うため物資源に働きかける創造的行為
・⇩42 人の営みが気候や生態系などの基礎的な環境条件に及ぼす影響
縦の帰りの流れ(↓)に関連のある用語について述べたページを以下に示す。
・横の帰りの流れ(→)
・縦の行きの流れ(↑)
・横の行きの流れ(←)
考え方全体の枠組みについて最初から述べたページを以下に示す。
・4つの流れ理論
